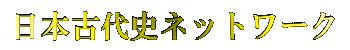古代史を解明する会(解明委員会)
活動記録 バックナンバー 9
- 「邪馬台国論争の解明」(2025/05/03)
- 日本書紀の紀年を復元する「無事績年削除法」(2025/06/14)
- 「邪馬台国・卑弥呼と天孫族の関係」(2025/07/19)(2025/07/22 New!)
- 「年輪年代測定法のデータ公開について」及び「取り上げるテーマ・題材について」(2025/08/16)(2025/08/24 New!)
- 「銅鏡と日本古代史」(2025/11/22)(2025/11/24 New!)
50.「邪馬台国論争の解明」(2025年5月3日)
2025年5月3日 13:00よりオンライン開催された。出席者11名
- テーマ
- 「邪馬台国論争の解明」
<構成>
- 1 丸地氏による説明
-
300年続いた邪馬台国の所在地論争を終結させたい。そのためには、魏志倭人伝の旅程を正確に解釈し、比定地を選定し、魏志倭人伝の記述との一致度を確認する。
所在地探しが行き詰まった原因は、唐津上陸説にある。よって、魏志倭人伝が中国の文献であることを前提に旅程についても史料批判を行う。
魏志倭人伝は、240年の梯儁の報告書・248年の張政の報告書、魏の公文書、裴松之の注、陳寿の加筆で構成されており、それぞれの記述箇所の同定を行う。
梯儁の報告書の邪馬台国への旅程は明瞭である。
陳寿が追記した投馬国は琉球であり、倭とは別の国であることを明らかにするため追記された。
書紀や魏志倭人伝の記述等から判断して、上陸地点は唐津ではなく消去法で博多である。それに基づいて比定すると、伊都は太宰府、奴国は筑紫神社付近、邪馬台国は筑後平野東部の広範囲。城山が卑弥呼の宮殿。短里による距離も一致。
卑弥呼の墓は祇園山古墳、台与の墓は焼ノ峠古墳。
- 2 質疑応答
-
- Q. 博多上陸説では、魏志倭人伝の国名と対応する地名はあるのか?
太宰府が伊都となるが、太宰府付近に「イト」の地名がある。マツラも同じ。 - Q. 魏志倭人伝に「東に海があり国がある」とあるが?
邪馬台国の人が使節にそう伝えたはず。 - Q. 魏軍の規模(数千名)は初訪としては大きすぎるのでは?
皇帝の命令なので大規模な軍勢だった。 - Q. 博多上陸説の比定地を確認してみたい。
- Q. 投馬国への起点が帯方郡ではなく、なぜ不弥国なのか?
起点に関する明確な根拠となる史料はない。
- Q. 博多上陸説では、魏志倭人伝の国名と対応する地名はあるのか?
動画と資料
- ➤ 動画 YouTube 動画リンク
-
-
「邪馬台国論争の解明」 97分
https://youtu.be/zk6n-Q6nuk0
-
「邪馬台国論争の解明」 97分
- ➤ 資料
-
- 「邪馬台国論争の解明」 丸地三郎氏 PDF 9.9MB
51.日本書紀の紀年を復元する「無事績年削除法」(2025年6月14日)
2025年6月14日 13:00 よりオンライン開催された。出席者8名
- テーマ
- 「『無事績年削除法』~新アプローチ法で『日本書紀』の紀年を復元する」
<構成>
- 1 伊藤雅文氏による説明
-
- 日本書紀の紀年は「真の歴史」とは異なっている。
- 天武天皇は「真の歴史」もとに原日本紀を編纂指示。さらに紀年を大幅に繰り上げた日本書紀が完成した。
- 紀年を復元する方法には、平均在位年数法、二倍年暦や古事記崩年干支を利用する方法があるが、それぞれ問題点がある。
- 無事績年削除法は、書紀のなかの事績のない年を省くことで、原日本紀を復元できる方法。天武は「春秋」に準じて無事績年のない史書を求めたはずだから。
- 原日本紀では、倭の五王と王朝並立(継体と仁賢・武烈)を隠すために、合計19年の無事績年が挿入された(第二期無事績年)。
- 日本書紀では、第9代までの天皇と神功皇后が創作され、各天皇の在位年数が無事績年の挿入により最長4.5倍に延長された(第一期無事績年)。
- 2 質疑応答
-
-
Q.神武即位を紀元前660年までに繰り上げた理由は?
持統朝になって遣唐使が再開され、中国が意識され繰り上げることとなった。初代天皇即位が301年。欠史8代を各120年引き伸ばすことで紀元前660年になった。意識したのか偶然かは分からない。 -
Q.初期は天皇制が整っていないため無事績年があるのではないか? 考古学の知見により、欠史8代以前の歴史が実在したことが裏付けられてきたので、創作されたものではない。
神代の時代の時代は創作ではなく実在したと考えている。
-
Q.神武即位を紀元前660年までに繰り上げた理由は?
動画と資料
- ➤ 動画 YouTube 動画リンク
-
-
「無事績年削除法」 49分
https://youtu.be/13EUr2QwVdA
-
「無事績年削除法」 49分
- ➤ 資料
-
- 「無事績年削除法」 伊藤雅文氏 PDF 3.0MB
52.「邪馬台国・卑弥呼と天孫族の関係」(2025年7月19日)
2025年7月19日13:00よりオンライン開催された。出席者8名。
- テーマ
- 「邪馬台国・卑弥呼と天孫族の関係」
<構成>
- 1 丸地三郎氏による説明
-
- 卑弥呼は、書紀上の登場人物の誰に擬製されるか、過去から議論があった。
- 史料批判とは、史料自体への検証と史料の中身の検証がある。
- 書紀は、神功皇后=卑弥呼であると誘導しているが信憑性はない。
- 記紀の記述は、考古学知見なども踏まえて整合性を取ることができる。
- 魏志倭人伝は、陳寿の追記箇所を取り除くことで、旅程が解明でき、邪馬台国の場所も明確になった。
- 記紀の古代史の記述順は発生順と異なっている箇所がある。
- 天孫族の本拠地は出雲族との戦争などがあり移転している。
- 北九州での最終決戦(倭国大乱)と出雲国譲りに勝利し、天孫族は全国支配に向けて神武東征を開始。
- 火明は、ニニギの兄だが、北九州の出雲拠点(遠賀川)に移り、その子孫のニギハヤヒは、大和へ移動した。
- 火照は、熊本に行き、隼人となった。
- 神武の東征は、ニギハヤヒとの対立から予想外の展開となった。遭難により、人材・文化を消失した。
- 北九州に残留した天孫族が卑弥呼を共立し、邪馬台国となった。防衛上の理由で朝倉付近に移動した。
- 狗奴国(隼人)との紛争は、張政の支援もあったが、東征した天孫族の招きにより大和へ移動し、終了した。
- 天照大神は1世紀の人物であり、3世紀の卑弥呼とは別人である。
- 2 質疑応答
-
-
Q.その後、九州の邪馬台国はどうなったか?
資料・情報は全くないが、まったく別に独立していたのでは? -
Q.出雲族の九州へのロジスティックスはどうなっていたか?
帆船もあったし、海岸沿いなら海流も弱いので、九州に行けたはず。 -
Q.香取・鹿島神宮が3世紀に存在したのか?
神社の由緒書きには、神武治世時の創建とある。氷川神社、香取・鹿島神社の分布から判断して、同様の時期から存在していた筈。
-
Q.その後、九州の邪馬台国はどうなったか?
動画と資料
- ➤ 動画 YouTube 動画リンク
-
-
「邪馬台国・卑弥呼と天孫族の関係」 104 分
https://youtu.be/qH5ouMHK15A
-
「邪馬台国・卑弥呼と天孫族の関係」 104 分
- ➤ 資料
-
- 「邪馬台国・卑弥呼と天孫族の関係」 丸地三郎氏 PDF 2.2MB
53.「年輪年代測定法のデータ公開について」及び「取り上げるテーマ・題材について」(2025年8月16日)
2025年8月16日 13:00よりオンライン開催された。出席者4名。
- テーマ
- 「年輪年代測定法のデータ公開について」及び「取り上げるテーマ・題材について」
<構成>
- 1 「年輪年代測定法のデータ公開」丸地三郎氏による説明
-
- 奈良文化財研究所から開示された年輪年代の情報開示について
- 暦年標準パターン:7種類の全数値データと、その作成の元となった樹木195本の年輪パターン
- 年代測定が行われた法隆寺心柱など5件に関して、史料の年輪パターンの数値及び、暦年標準パターン
- 奈文研が開示した時期は、本年5月28日 公開は6月上旬
- ホームページのページを開きながら、内容の紹介を行った。
- 開示に際し、追加検証の情報の共有を目的として「年輪検証の意見交換コーナー」を設けた。
- その結果、複数の方の検証方法や成果が寄せられた。
- 数学やプログラムに長けた方々が参加され、検証用のプログラムを公開してくれ、検証結果を掲載してもらえた。
- 開示されたデータ自体を使って確認した結果は、光谷氏が昨年7月の再調査結果発表を含めて、整合性は取れている様子。
- 開示されたデータを発表された元の書籍/記事と整合すると不可解なことが有り、調査中。
- 控訴審について
- 下記の件に付き控訴を行ったが、棄却された。敗訴。
- 奈文研に保管されていた紙に描かれたグラフデータ及び数値の記載された書面
- 正倉院関係のデータ・文書
- 弁護士と相談し、再上訴しないこととした。
- 控訴審の判決中で下記の主旨の部分があったことは、成果と云える。
ガイドラインにより基礎試料を保存しておくことが望ましかったとしても、基礎試料を保存しておくことが法令により義務づけられていたわけではないため、基礎試料が業務状必要なものとして、実際に利用又は保存されていたものとは認められない。
- 上訴時に「今後の開示請求に際し、検証用の基礎試料の開示」は、認められないのではとの心配は、控訴審では、基本的には認められるとの判断があり、心配は杞憂に終わった。
- 今回の奈文研の場合には、余りにも雑な扱いで、「法人文書」と云えない、書類とは認められない残滓物と判断され、開示対象とされなかった。平成26年(2013年)の「研究活動における不正行為等に関するガイドライン」に示された「基礎試料」の保存と開示は、認められたことになる。
- 下記の件に付き控訴を行ったが、棄却された。敗訴。
- 奈良文化財研究所から開示された年輪年代の情報開示について
- 2 質疑応答
-
- 年輪年代の学会/専門家が調査・検討することが望まれるとの意見が出た。
- 樹木年輪研究会という団体があり、コンタクトができた処。
- その外の、学会の意見が欲しい。考古学関係者は、訴訟絡みのことは敬遠している。
- 今後、私達で調べること、学会などとの連携を試みることにした。
- 年輪年代の学会/専門家が調査・検討することが望まれるとの意見が出た。
- 3 「取り上げるテーマ・題材について」
-
- 当会の毎月開催が難しくなった。
- 主体的に活動してきた丸地の時間的制約ができた。(健康上の問題もある。)
- 3か月に一回が提案された。
- 解明したい課題としては、「鉄」、「銅鐸」、「鏡」、「古墳」、「神社」、など
- 発表者は、丸地以外の方の発表を多くする。
- 次回は11月15日(土)清水徹朗氏 「鏡」概要調査を行い、まとめて発表する。皆さんの意見を聞きたい。
- 次々回は2026年2月(日にち未定)可児俊信氏「伊勢神宮」
- 当会の毎月開催が難しくなった。
動画と資料
今回は、動画と資料の発表は、無しとします。
54.「銅鏡と日本古代史」(2025年11月22日)
2025年11月22日 13:00よりオンライン開催された。出席者5名。
- テーマ
-
「銅鏡と日本古代史」
その他に、奈文研からの年輪年代法のデータ開示報告、「銅鏡と日本古代史」へのコメント
<構成>
- 1 「銅鏡と日本古代史」清水徹朗氏による説明
- <説明>
-
- 銅鏡、とりわけ三角縁神獣鏡は、邪馬台国畿内説の根拠となっており、古代史において重要。
- 銅鏡製作地によって、中国鏡と倭製鏡に分かれる。また文様によっても多くの種類に分類できる。
- 弥生期に銅鏡の日本での出土は、3/4が九州出土、畿内はほとんどない
- 1953年、畿内で出土した30面以上の三角縁神獣鏡を小林行雄氏が、卑弥呼が受け取った100枚の銅鏡の一部とし、畿内説の有力根拠とした。
- その後も、京都大学の研究者を中心に、三角縁神獣鏡が卑弥呼の鏡であるする説を出し、畿内説を補強した。
- <質疑応答>
-
- 銅鏡を分類する理由 製作地、製作時期、製作した工人を特定するため
- 2 奈文研からの年輪年代法のデータ開示報告
- 3「銅鏡と日本古代史」へのコメント
- 第Ⅰ次大激変 280年に呉が滅び、華南の銅が華北に流れ込み、それ以降の銅鏡は華南の銅製である。
- 第Ⅱ次大激変 4世紀前半に、鏡の中心的分布が北部九州から、畿内に移行した。
- 三角縁神獣鏡の銅は、華南の銅製であるから、280年以降の製作であり、卑弥呼の鏡ではないことは明らか。
動画と資料
- ➤ 動画 YouTube 動画リンク
-
-
「銅鏡と日本古代史」 61分
https://youtu.be/TL0R40pMook
※以下を含む- 奈文研からの年輪年代法のデータ開示報告 (9分)
- 「銅鏡と日本古代史」へのコメント (8分)
-
「銅鏡と日本古代史」 61分
- ➤ 資料
-
- 「銅鏡と日本古代史」 清水徹朗氏 PDF 2.2MB
- 奈文研からの年輪年代法のデータ開示報告 丸地三郎氏 PDF 1.2MB
- 「銅鏡と日本古代史」へのコメント 丸地三郎氏 PDF 1.7MB