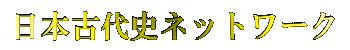古代史を解明する会(解明委員会)
活動記録 バックナンバー 8
- 「日本語・琉球祖語から見た日本人の起源」(2024/09/14)
- 「土井ヶ浜遺跡の人骨DNA解析結果」(2024/11/09)
- 「新聞記事を見ながら日本人の起源を検討」(2024/12/07)
- 「日本人の起源~最新のDNA成果を反映する」(2025/01/18)
(2025/02/09 New!) - 「一部勝訴! 年輪年代法の情報公開請求裁判の報告と今後の方針」(2025/02/22)
(2025/03/03 New!) - 邪馬台国論争を振り返る~「邪馬台国論争と日本国家の起源」(2025/03/15)
(2025/04/12 New!)
44.「日本語・琉球祖語から見た日本人の起源」(2024年9月14日)
第44回古代史を解明する会は 2024年9月14日 13:00 よりオンライン開催された。出席者6名。
- テーマ
- 「日本語・琉球祖語から見た日本人の起源」
日本語・琉球祖語から見た日本人の起源~「日本語・琉球諸語による歴史比較言語学」の出版を機会に、『歴史比較言語学』の「成果」を紹介する記事として、著者の一人トマ ペラール氏へのインタビュー記事が出た。今回はその書籍の紹介ではなく、「歴史比較言語学の成果」を紹介するインタビュー記事を取り上げた。
- <構成>
-
- 丸地三郎氏による資料「日本語・琉球祖語から見た日本人の起源」の解説
- 質疑応答
1 丸地三郎氏による資料「日本語・琉球祖語から見た日本人の起源」の解説
「日本語・琉球諸語による歴史比較言語学」が出版され、そのインタビュー記事では、比較言語学の研究成果から、以下の4点が示された。なお、琉球諸語は、沖縄・奄美の言語の総称である。
- (中国大陸から)日本語・琉球諸語の祖語を持った民族が、水田稲作をもって朝鮮半島へ移動した。根拠は日琉祖語の単語の半島への残存。
- 半島から日本へ移住した。
- さらに九州から琉球へ移動した。
- 稲作が日本列島に伝えられた紀元前10世紀から紀元後3世紀頃の時点では、水田稲作用語は、日本語と琉球諸語は分岐しておらず、日本語と琉球諸語は、その後の3~6世紀に分岐した。
- ① への反論
- 2023年8月の当会の資料32.「古代朝鮮と日本の歴史」を示し、根拠の単語残存時期の7世紀以前に、稲作の弥生人が長期間、日本から朝鮮半島へ移住したことが歴然としてあり、単語残存は、朝鮮半島が先とする証拠となり得ない。
- ② への反論
- 弥生渡来民が水田稲作を、直接日本に広めた。日本から弥生渡来民が半島へ移住し、稲作を広めた。「古代朝鮮と日本の歴史」では、この事実を示した。
- ③ への反論
- 水田稲作をもって沖縄へ進出したとし、著者の一人は、九州・琉球諸島では、言語がマトリョーシカ分布(複数の言語か入れ子状に分布し交わっていない状態)しており、九州から民族が移動したとしているとの根拠を示しているが、実際には、本土との貝製品の活発な交流は存在したが、沖縄に稲作が広まった痕跡は存在しない。稲作が始まったのは早くとも10世紀または島津支配以後である。
- ④ への反論
- 水田稲作が行われていなかった紀元前10世紀から紀元後3世紀頃の時点では、沖縄では水田稲作に関する語が存在せず、分岐の論議自体が成り立たない。
トマ ペラール氏の8世紀の時点では、日本語と琉球語は分岐していたとの論文の結論は高く評価するが、インタビュー記事は、論拠が成り立たない。
最近の古代人DNA解析など、複数の論拠から、かなり古い時代に、琉球諸語の話者が、本土より先に琉球諸島に到来していたことが推察されることが示された。
2 質疑応答
- 沖縄は石灰岩の土地であるうえ、津波・台風もあることから遺跡が残りにくい
- 用語(西北九州縄文人、倭人、弥生等)の定義を明確にすることで、議論が明確になる
- 黒潮があるため、鹿児島から沖縄列島に行くのは紀元前後の技術的に難しい
動画と資料
- ➤ 動画 YouTube 動画リンク
-
-
「日本語・琉球祖語から見た日本人の起源」 101分
https://youtu.be/_1_hzlegDJ4
-
「日本語・琉球祖語から見た日本人の起源」 101分
- ➤ 資料
-
- 「日本語・琉球祖語から見た日本人の起源」 丸地三郎氏 PDF約 4.2MB
45.「土井ヶ浜遺跡の人骨DNA解析結果」(2024年11月9日)
第45回古代史を解明する会は 2024年11月9日 13:00 よりオンライン開催された。出席者7名。
- テーマ
- 「土井ヶ浜遺跡の人骨DNA解析結果」
土井ヶ浜遺跡の人骨DNA解析結果「土井ヶ浜遺跡の弥生人の遺伝子解析により、日本列島への移民の起源に関する知見が得られる」 発表論文の論評
- <構成>
-
- 丸地三郎氏によるプレスリリースされた論文の紹介と論評
- 質疑応答
1 丸地三郎氏によるプレスリリースされた論文の紹介と論評
- 2024年10月に東邦大・東大等の研究者による「土井ヶ浜遺跡の人骨DNA解析結果」が発表され、以下の2点が報告されている。
- 土井ヶ浜のゲノムデータが弥生時代人の代表である。又、従来、代表扱いされた下本山岩陰遺跡のゲノムデータは弥生時代人の代表ではない。
- 弥生時代に渡来した人が、縄文人と混血し、現代日本人の祖先集団が誕生したが、その渡来元が朝鮮半島であるとした。
- 東邦大学プレスリリース(発行No.1410 令和6年10月15日)
-
「弥生時代人の古代ゲノム解析から渡来人のルーツを探る」
https://www.toho-u.ac.jp/press/2024_index/20241015-1410.html - 英文論文(「Journal of Human Genetics」誌掲載)
-
「Genetic analysis of a Yayoi individual from the Doigahama site provides insights into the origins of immigrants to the Japanese Archipelago」
https://www.nature.com/articles/s10038-024-01295-w
この2点に付いて論評
- ① については高く評価する。
-
- その三重構造論は、DNA解析した論文が契機となっている。
- その論文では、弥生を代表するゲノムデータとして、下本山岩陰遺跡人のものを採用したことから成り立っていた。
- 弥生人を代表するゲノムデータが変わることで、三重構造論は否定される。
- もともと、下本山岩陰遺跡人のDNA解析した論文には、弥生人を代表しないと記載されていた。
- ② については、論文主旨を否定する。
-
- 発表論文では、土井ヶ浜弥生人と遺伝的に最も高い類似性を示したものが古韓国人集団のDNAであることを理由としている。
- しかし、古韓国人集団について、概要も年代も示さず、断定しており、理由・証拠にはならない。
- そこで、論文の著者に問い合わせ、概要・年代について知らせてもらい、確認した処、
- 出土遺物は、日本人由来の甕棺/前方後円墳であった。
- 古韓国人集団の金海/郡山のDNA採取遺跡の位置が判明し、年代は1700年前~1500年前と判明した。
- 古韓国人集団の金海/郡山の出土人骨で、Y-DNAは、日本人を代表するD1a/O1b2で、mt-DNAも日本の弥生人に多い型が検出された。
- 土井ガ浜人のDNAが2300年前であり、600年以上後であることから、日本から半島に渡った集団と考えることが妥当。
- 土井ガ浜人よりも古韓国人集団が時代的に、同時期又は前ならば、論文著者の理由は成り立つが、600年以上後の時代では、理由として成り立たない。
古代の日本と韓国の交流の見直しについて、2023年8月に発表した資料を改めて掲げ、解説し、否定する理由・背景を説明した。
2 質疑応答
- 土井ヶ浜だけのデータで結論づけては、誤る可能性がある。
- ANS:土井ヶ浜以外からの同様のデータもあり、複数のDNAデータから結論づけている。当論文以外にも、複数の弥生人のDNAの論文が発表されており、妥当な評価と考える。
- 半島は最近まで米も作れなかった地域であり、そこに住んでいた人が、水田稲作をもって日本列島に来たというのは考えにくい。
- 当時のことを議論するには、当時の地形・地図を前提にすべき。
- 弥生・縄文人は、時代と形質を分けて議論しないと議論が進まない。
動画と資料
- ➤ 動画 YouTube 動画リンク
-
-
「土井ヶ浜遺跡の人骨DNA解析結果」 84分
https://youtu.be/BusV6kFzPjM
-
「土井ヶ浜遺跡の人骨DNA解析結果」 84分
- ➤ 資料
-
- 「土井ヶ浜遺跡の人骨DNA解析結果」 丸地三郎氏 PDF約 4.4MB
46.「新聞記事を見ながら日本人の起源を検討」(2024年12月7日)
2024年12月7日 13:00よりオンライン開催された。出席者4名
- テーマ
-
「新聞記事を見ながら日本人の起源を検討」
新聞の記事をもとに、日本人の起源について検討した。
- <構成>
-
丸地三郎氏によるPPT資料の説明
日本人の起源に関する朝日新聞(2020.12.1)と読売新聞(2024.2.7)の記事の内容を紹介し、課題となったテーマを見直し、再検討した。
記事解説とコメント
- <朝日新聞の記事>
-
- 愛知県の伊川津貝塚遺跡の縄文人の人骨からDNAを抽出できた。アフリカからアジア東部そして日本へのルートについて、このDNAゲノムを使って、解析を行った。
- 東アジアに来た人類の移動ルートには、ヒマラヤの北ルート説と南ルート説が有ったが、この解析から、北ルートは無く、南ルートを通り、東アジア及び日本人が到来したことが判った。
- <朝日記事へのコメント>
-
- 4年前の2020年記事だが、その元となったDNAの論文発表が出てから、北ルートが無いことが主流となり、ネット上では、かつて主流だった北ルートを記した地図や論説が激減したことに驚く。
- 南ルートだけが正しいとして残った理由は、今回のゲノム解析の結果と、もう一つの大きな理由がある。DNA学会の国際協力の結果、アジア人の古代人を含む約2000人のDNAを解析し、アジア系の系統樹が作られた。そこに、北ルートの影響が全くなかったことが挙げられる。これが大きな理由。
- DNAによる人類起源の研究成果は有効であることは判ったが、日本では2016年に始まったばかりで、抽出と解析ができたサンプル数がまだ少ない。日本への到来時期が4万年前にも拘らず、検出できたサンプルは、約4000年前が最古で、解析の材料はまだまだ不足している。
- アジアへは南ルートで到達していることが判明したことは、ニュース価値が高い。
- <読売新聞の記事>
-
- 日本人の起源の紹介に、氷河期に存在したスンダ・ランドを大きく取り上げた。
- 2万年前の海進期にスンダ・ランドが水没し、舟で人々は脱出し、日本に人類が到達した。
- 日本人は「黒潮の民」であったと紹介。
- その他に北方ルート、朝鮮ルートを紹介。
- 南鹿児島の栫ノ原遺跡や上野原遺跡と、丸木舟を製作用の丸ノミ型石斧や平底型石器などを紹介し、「黒潮の民」であったこと示した。更に、7300年前の鬼界カルデラ爆発の被害に遭い、南鹿児島から舟で脱出した人々が、四国・本州にその文化を伝えたことを記載。
- 南太平洋のバヌアツと南米エクアドルで、縄文土器又は類似した土器が出土したことから、太平洋沿岸にまで、黒潮の民の移動痕跡が残ることを記し、日本人祖先のフロンテア精神を讃えた。
- <読売記事へのコメント>
-
- スンダ・ランドを紹介してくれたことに感謝。
- 日本人は黒潮の民であることに賛意を表する。
- 前回の土井ガ浜の新聞記事紹介時に新しい証拠が見つかり、次のことを示した。
- 日本人祖先が北海道から樺太・シベリヤへ進出し、長くシベリヤなどに留まったこと、
- 無人の地であった朝鮮半島には、日本先住民の縄文人が進出し、多くの黒曜石の石器を含む遺跡を遺し、永いこと居住したことが判明したことを改めて紹介し、
- 読売の記事に記された北方、半島ルートは有り得ないとした。
- 南鹿児島の二つの遺跡の人々は、丸のみ型石斧からも沖縄からの黒潮の民であることが判る。
- 鬼界カルデラ噴火だけでなく、姶良カルデラ噴火の影響も考慮すべき。
動画と資料
- ➤ 動画 YouTube 動画リンク
-
-
「新聞記事を見ながら日本人の起源を検討」 102分
https://youtu.be/odcfGHvxhNg
-
「新聞記事を見ながら日本人の起源を検討」 102分
- ➤ 資料
-
- 「新聞記事を見ながら日本人の起源を検討」 丸地三郎氏 PDF約 3.9MB
47.「日本人の起源~最新のDNA成果を反映する」(2025年1月18日)
2025年1月18日 13:00よりオンライン開催された。出席者7名
- テーマ
- 「日本人の起源~最新のDNA成果を反映する」
<構成>
- 丸地三郎氏によるPPT資料の説明
-
日本人の起源に関して、2021年に「日本人の起源」基本レポートを発表し紹介した。その後、2021年から2025年の間に新しく判明した事実は、①~⑧が挙げられるので、紹介し、新しい事実を踏まえた考え方を紹介する。
- 人類の出アフリカのルート シナイ半島経由であることが判明。アラビア半島経由説もあったが、アラビア半島にはいないはずのネアンデルタール人とホモサピエンスが交配していることが判明したためルートが確定。
- 人類のヒマラヤ移動ルーツ DNA解析によって、ヒマラヤの北ルートでアジアへ移動したとする説は、なかったと判明。
- 人類の日本への渡来ルートの3ルート
- シベリア・サハリンルート 日本先住民が北海道からサハリン・シベリアへ移動し、13-14世紀まで活動していた。サハリンからの北海道への移動の痕跡はない。
- 朝鮮ルート 韓国の考古学の成果では、旧人の痕跡は残るが、それ以降は、日本の先住民が半島へ移動しのこした遺跡しかない。従って、半島からは渡来していない。
- 台湾ルート 台湾からは黒潮を渡る実験には成功したが、民族移動としては否定的な見解が残る。
- スンダランドルート 4万年前に帆付舟で黒潮に乗り日本に来たとするのは有力。
- 凡5万年前に、スンダランドからオーストラリア等に移動した新人がおり、帆つきの舟又は筏を使用したと人類学者の説が有力。
- フィリピンから日本への移動実験は多く成功。旧日本兵も、同ルートで帰還。
- Y染色体のハプログループの系統図でも、オーストラリアに移住したと同じ初期の変異グループが日本の先住民で、両方のグループの人達が、帆つきの舟で航海しても、無理はない。
- 沖縄の古代人の死滅/移住説 琉球・沖縄の古代史を支配してきた説が、最近の発掘成果により、根拠が失われた。その結果、現在のネット上では、死滅/移住説は無くなった。沖縄・琉球の歴史は、発掘された人骨の人々が子孫を残し、現代まで続くこととなる。
- 日本人三重構造説 弥生人DNAモデルの誤った取り扱いが指摘され、三重構造説は否定された。
- 九州の縄文人に、弥生渡来人のDNAが混在することが判明。 韓国南岸(九州に近い)からも古い人骨(6400年前)のDNAが解析され、縄文人と弥生人の混血であったことが判明。今までの概念では有り得ないことが判明した。
- タカラガイの産地について
- 沖縄のタカラガイが中国の通貨として使用されていた。中国で通貨として使われたタカラガイは、紐を通す穴開け加工があったことが判明した。BC5千年頃に、硬い貝にきれいな穴を明けると云う高度な加工技術を持った民族の存在が不可欠だった。日本海をも、交易範囲としていた沖縄の縄文人の有した技術と推定される。
- 沖縄の古代人絶滅論が消滅し、弥生人のDNAが九州の縄文人・朝鮮半島南部に古代人に存在すること、宝貝が沖縄産であることから弥生人のDNAを持つ民族が、BC5千年頃には、沖縄に移住し、琉球祖語を使いながら、宝貝の養殖を行い、縄文人と混血して、現在の沖縄人のDNAの構成を築いたものとする論を展開した。
- 日本人二重構造説を図表にした埴原論文の図を改良した新しい図を提起した。
- 日本人の起源を検討するには、重要なポイントとして、「黒潮に隔てらえた海洋国であること」と、「日本ではある時から母国語が別の言語に置き換わったこと」の2点を強調した。
<質疑応答>
- タカラガイはいつ頃まで通貨として使われていたか?
- 産総研の降灰の地域分布は、九州の風向きと一致しない。
- 海の向こうに陸地があるか分からないのに、スンダランドから船で海に乗り出すだろうか。やはり半島から日本に来たのではないか?
- 気候が温暖化する時期に、南に向かうのはおかしくないか?
- 最寒冷期に対馬海峡は大陸と陸続きだったのか?
動画と資料
- ➤ 動画 YouTube 動画リンク
-
-
「日本人の起源~最新のDNA成果を反映する」 129分
https://youtu.be/nbrqjD5jSww
-
「日本人の起源~最新のDNA成果を反映する」 129分
- ➤ 資料
-
- 「日本人の起源~最新のDNA成果を反映する」 丸地三郎氏 PDF約 6.4MB
48.「一部勝訴!年輪年代法の情報公開請求裁判の報告と今後の方針」(2025年2月22日)
2025年2月22日 13:00よりオンライン開催された。出席者13名
- テーマ
- 「一部勝訴!年輪年代法の情報公開請求裁判の報告と今後の方針」
<構成>
- 1 井上弁護士によるPPT資料の説明
-
- 1983年に奈文研がひのき暦年標準パターンを完成し発表したが、その後、暦年標準パターン、基礎資料、照合データが公開されないため、追加検証ができないうえ、奈文研が独占的に木材年輪年代測定を実施していると問題が発生している。
- 文科省(2014年)の研究活動ガイドラインでは、追加検証を可能とするため検証可能なデータの公開と求めている。
- 奈文研の担当者光谷氏に情報開示を求めたが開示されず、やむを得ず訴訟に至った。
- 判決では、暦年標準パターンの数値データは開示が認められたが、それ以外の画像データ、試料、建築部材との照合データは、奈文研は組織的に用いている者ではないという理由で、開示が認められなかった。
- すべてのデータが開示されなかったため、追加検証ができない等影響が残る。
- すべての開示を求めて控訴する。
- 2 丸地三郎氏による追加説明
-
- 訴訟目的は、①奈文研より公開された年輪年代の基礎情報を一般公開し追加検証を可能とすること、② 国・公立の研究機関の研究発表に関わる情報を、情報公開請求によって入手可能とすること、③ 国・公立の研究機関が、自発的に研究の基礎情報を公開するよう社会にアッピールし実現したい。
- 裁判の経緯 2022年1月提訴、24回の公判後、2025年1月結審
- 訴訟対策として、奈文研は、2024年12月に一部の年輪データを公開した。公開の目的を第3者の追検証を可能にすることとし、自発的に基礎情報を公開するとした。
- 2024年7月に光谷氏も池上曽根遺跡での年代測定ミスを自ら公表した。開示された場合に最初に問題となる件に先手を打って、年代の訂正を行ったものと見られる。
- 考古学者の寺澤薫氏は、
データが開示されて追加検証ができるのはよいこと
とコメント。
- 3 山内千里氏によるまとめ
-
- 別途記した文章が有りますのでそれをご参照下さい。
- 4 質疑応答
-
- Q.年代測定法は信頼できるのか? どんな測定法が有るのか?
科学的な方法としては、年輪年代/酸素同位体年輪年代法/炭素14年輪年代法などが有る。従来からの年利測定法は、土器編年/青銅器編年がある。これらは確定的とは言えないが、有効な方法。但し、年代の単位が最も細かく考えても30年が一つの単位。科学的年代法は、国際的には複数の国の学者が検証した上で年代決定しており、信頼性が高い。しかし、日本では、検証が行われていないため、信頼性に欠ける。木材の年輪年代法が、外の酸素同位体/炭素同位体の年輪年代測定法の機銃となっているため、残念ながら信頼性に欠ける。水月湖の年縞に関しては、国際的な学問機関が検証しており信頼性が有る。7万年分の年縞と年代が確定しているため、期待は大きい。
- Q.研究機関に対する研究データの情報公開の裁判例はあるのか?
学問に関連した研究データに関する事例は見当たらない。初めての事例になる。
- Q.情報公開の対象となる文書に関して、組織的に用いられるという条件が判決で示されたが、どうなるのか?
井上弁護士:この点は控訴審で戦いたい。このまま決定すると、情報公開が不十分なことになり、今後の悪影響が懸念される。
- Q.一審の判決で電子データは開示する決定がされたが、奈文研側が控訴しないことが確定したので、この部分は確定したことになるのか?
井上弁護士:確定した。奈文研は、不開示の決定を取り消して、改めて開示の手続きを行うことになる。
- Q.高裁の決定に関係なく開示が認められるのか?
井上弁護士:認められる。
- Q.高裁の決定に関係なく開示が認められるのか?
- 奈文研から電子データが公開されたら、日本古代史ネットワークとしては、そのデータを公開する。そのデータの解析を私どもとしても解析して行きたい。一緒に、データ解析する人を探している。現在、二人の方がやろうと云ってくれている。外にも居るようだったら、教えて下さい。
- 民間の任意団体がこう言ったことをやるのではなく、学問団体が、こういった検証を行うべきではと思う。例えば、日本文化財科学会など。奈良大学の人が会長を務めている。
- 考古学者の寺沢さんは、今回の裁判に関して、回答してくれているが、年輪年代法を成果を取り入れて、弥生から古墳時代の年代を変更された学者の方々のご意見を聞かせて貰いたいと意見が出た。また、賛成する人が多かった。
- Q.年代測定法は信頼できるのか? どんな測定法が有るのか?
動画と資料
- ➤ 動画 YouTube 動画リンク
-
-
「一部勝訴!年輪年代法の情報公開請求裁判の報告と今後の方針」 41分
https://youtu.be/wH_7H9JjkTQ
-
「一部勝訴!年輪年代法の情報公開請求裁判の報告と今後の方針」 41分
- ➤ 資料
-
- 「奈文研の暦年標準パターンに関する問題提起」 井上弁護士 PDF 3.7MB
- 「一部勝訴報告」 丸地三郎氏 PDF 0.8MB
49.「邪馬台国論争を振り返る~邪馬台国論争と日本国家の起源」(2025年3月15日)
2025年3月15日 13:00よりオンライン開催された。出席者12名
- テーマ
- 「邪馬台国論争を振り返る~邪馬台国論争と日本国家の起源」
<構成>
- 1 清水氏による資料の説明
-
- 邪馬台国とは何か
- 邪馬台国問題はなぜ重要か
- 邪馬台国論争の争点 行程論が論争
- 研究・論争の歴史 江戸時代から現代まで継続している。銅鏡や古墳も研究されている。専門家は古代国家形成史に関心が移り、アマチュアが議論している。年輪年代法により近畿説が有力になった。直近では近畿説はありえないという議論もある。
- 鷲崎弘朋の邪馬台国論 『邪馬台国の所在地と日本国家の起源』の紹介
- 邪馬台国と記紀神話
- 日本国家の起源と古代国家の形成
- 2 質疑応答
-
-
魏志倭人伝の行程記事はどの程度、信じられるか?
数字は正確ではないのでは?書き間違えもある。
行程記事の水行/陸行(不弥国→投馬国→邪馬台国)は本来は里数(1300里)が書かれていた。邪馬台国は熊本平野となる。裴松之拝が429年に表した三国志の注釈書では、水行/陸行の箇所に注釈が付いていない。つまりこの時点では里数が書かれていたことになる。三国志の「会稽東治の東」の箇所が後漢書(430年)で「会稽東冶の東」に誤記された。誤記された場所への行程に合わせるため、1300里の箇所が水行/陸行に書替えられた。 - 地名等の固有名詞の読み方は、漢音に引きずられず4世紀当時の発音で読むべき。邪馬台国の台を「タイ」と読むのは後世の発音である。当時の発音は「デグ」に近い音(dəg/ťəg/diəg)。邪馬台国の場所は朝倉市付近。
- 会稽東冶を船出すると、黒潮に流されて,沖縄ではなく九州に着くはず。強い西風であれば沖縄に着く。
- 会稽東治の記事は、一寸千里法で計測されたので位置は正しいはず。
- 卑弥呼と天照大神の時代と場所は?卑弥呼の権威を利用して天照大神を創り上げられた。
- 中国研究者が書いた日本の古代史の見解を重視すべき。中国は日本で軍事行動をしたはず。中国の使節は数千人単位だから張政もその規模なので、ロジの観点で近畿までは行けず邪馬台国は北九州でしかありえない。中国からみて軍事的は北部九州が重要。中国研究者はみな九州説(宇佐、吉野ヶ里、伊都の三角形の中)。呉と狗奴国が組んで邪馬台国に対抗した可能性もある。銅鏡を理由に近畿説とするのは些事に過ぎない。
- 中国は日本に進駐し、伊都国に常駐していた(漢伝?)。日本のことはよく知られていた。陳寿は司馬仲達を持ち上げて書いている。
- 魏志倭人伝では「男が少ない」と書かれている。男性が東征したためか。
- 宇佐八幡宮は騎馬民族がつくったのではないか。
-
魏志倭人伝の行程記事はどの程度、信じられるか?
動画と資料
- ➤ 動画 YouTube 動画リンク
-
-
「邪馬台国論争を振り返る~邪馬台国と日本国家の起源」 56分
https://www.youtube.com/watch?v=FqsiOoIxDa4
-
「邪馬台国論争を振り返る~邪馬台国と日本国家の起源」 56分
- ➤ 資料
-
- 「邪馬台国論争を振り返る」 清水徹朗氏 PDF 1.6MB