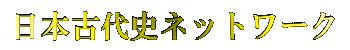古代史を解明する会(解明委員会)
活動記録 バックナンバー 6
- 「古代朝鮮と日本の歴史」2023年8月12日 東京 実施済
- 「西遼河起源説+𝛼」2023年9月9日 東京 実施済
- 「天孫降臨と史実の関係」2023年10月7日 東京 実施済
- 「邪馬台国と高天原の関係」2023年11月11日 東京 実施済
- 「日向三代の記述の理由」2023年12月9日 東京 実施済
- 「文献と考古資料の対応:天孫降臨・日向三代」2024年1月13日 東京 実施済
32.「古代朝鮮と日本の歴史」(2023年8月12日)
2023年8月12日 32回 古代史を解明する会「古代朝鮮と日本の関係」は、13:00よりオンライン開催された。出席者10名。
- テーマ
- 「古代朝鮮と日本の歴史」
5月度に引き続き、古代朝鮮の歴史を改めて振り返る。従来の考古学の常識では、人・物・文化は全て朝鮮半島から日本へ移動したとされてきた。韓国の教科書など韓国側の資料や、日本側の特に九州関係の論文・書籍を見直し、最近の弥生土器に関する研究成果を加味すると、稲作、土器、文化等は朝鮮から一方的に日本に伝播したのではなく、日本から朝鮮への伝播が多かったことが分ってきたので、最新研究成果を報告する。
- <構成>
-
- 丸地三郎氏によるPPTを用いた解説と古代朝鮮に関連する課題へのコメント
<1 解説>動画あり
- 韓国における古代史認識を教科書から確認すると、古朝鮮のエリアは遼東・満州・北朝鮮の領域に限定されおり、半島南部は歴史的に空白となっている。
- 紀元前6000年以降は,朝鮮半島全域に、石器・日本産黒曜石・縄文土器が出土し、九州と同じ縄文人が居住していた。半島の土器は、九州南部で1万年以上前から出土するタイプの縄文土器と類似。(東北産の縄文土器とは異なる。)
- 7300年前の鬼界カルデラ爆発以降、九州・熊本の轟式土器が、山陰・山陽と朝鮮半島半部へ拡散。紀元前5000年頃(7000年前)、櫛目文土器が朝鮮半島全土に瞬く間に広がった。
- 中国歴史書では、紀元前1046年以降に、中国の殷王朝の一族が、古朝鮮を成立させたとする。古朝鮮のエリアは戦争に長けた中国からの移民が支配。その地域に居た縄文人は南へ退避したものと推定される。
- 空白とされていた朝鮮半島南西部には、中国長江下流域から水田稲作・支石墓が伝播した。その中心的な遺跡が松菊里遺跡であった。その松菊里から水田稲作、支石墓、青銅製剣が日本に伝わった。
- 松菊里から水田稲作・支石墓等が伝わった日本の九州北部では、土器に関しては、日本在来の縄文土器の発展形である突帯文土器が使われ、半島からの土器では無かった。水田稲作を伝えた主体は縄文人であった。
- その後、別途、水田稲作を持って倭人が渡来し、弥生渡来人となり、弥生土器と文化が伝わった。
- 朝鮮半島では、出土数の少なかった弥生系土器であるが、近年半島南部の勒島遺跡などで発掘調査が行われ、出土例が劇的に増加し、考古学として統計処理の適用が可能となり、新たな論文が生まれた。その結果、城ノ越式/須玖I/II式などの弥生式土器=遠賀川式土器が、九州から壱岐島・原の辻遺跡を経由し半島南部の勒島遺跡に移動したことが判明した。
- 紀元前から倭人が移住し、日本から朝鮮半島南部へ弥生式土器、文化が流入した。
- 朝鮮歴史書「三国史記」には複数の倭人が新羅王となったことが記されている。
- 以上のことを踏まえて、半島と日本の関係を、年代と地域の両面から分かる年表を提示した。
- 朝鮮半島と日本の交流を見直すと、① BC6000から、日本・九州から縄文人が半島へ。② BC850~300年の時期に中国長江河口流域から水田稲作・支石墓等が朝鮮半島南部の松菊里に伝わり、その水田稲作・支石墓が縄文人によって九州北部へ伝えられた。③ その後、倭人が別の水田稲作技術と弥生文化を持って九州及び日本へ渡来し、縄文人を退け、主体となった。弥生土器及び弥生文化は、九州北部から壱岐を経由して、半島南部へ流入した。
- 従来、「朝鮮半島から日本へ」一方的に文化・技術が伝播したとされた常識が覆り、縄文・弥生時代から古墳時代開始時期までの時代では、「日本から朝鮮半島へ」の流れが主であった。
こうした知見から、提起されている課題にコメントした。
- キビ・ヒエ・アワは、縄文人が、イネ(熱帯ジャポニカ米)を含めて日本で先に栽培しており、「日本から朝鮮へ」伝播した。
- 縄文から弥生への移行に際して、朝鮮半島からの渡来人の役割はとの課題については、一次の水田稲作は、「半島から日本」へ来たので、影響は有ったが、それ以降の二次の水田稲作の到来時には、一次到来の稲の品種は廃絶され、影響が無くなり、弥生時代に入ってからは、「日本から半島へ」弥生土器などの文物が伝播した。従って、渡来人が日本へ与えた影響は限定的。
- 縄文・弥生の時代には、朝鮮からの遺伝学的影響は無い。また、騎馬民族渡来説はあり得ない。
- 大和政権の成立・発展期には、文物の流れは、「日本から朝鮮へ」で、朝鮮からの影響はない。
- 記紀にある半島からの渡来人の影響は限定的。出雲一族も半島との交流は限定的。
- これまでの一方的な半島からの流入という見方を考古学的にも改めるべき。
動画と資料
- ➤ 動画 YouTube 動画リンク
-
-
「古代朝鮮と日本の歴史」 丸地三郎 140分
https://youtu.be/WyHAJTojOys
-
「古代朝鮮と日本の歴史」 丸地三郎 140分
- ➤ 資料
-
- 「古代朝鮮と日本の歴史」 丸地三郎 PDF約 7.3MB
33.「西遼河起源説とその撤回要請及び朝鮮半島と日本に関する2冊の書籍:論評」(2023年9月9日)
2023年9月9日 33回 古代史を解明する会「西遼河起源説とその撤回要請及び朝鮮半島と日本に関する2冊の書籍:論評」は、13:00よりオンライン開催された。出席者12名。
- <構成>
-
- 丸地三郎氏によるPPTを用いた解説
- 解説に対する質疑応答
- <テーマ>
- 「西遼河起源説とその撤回要請及び朝鮮半島と日本に関する2冊の書籍:論評」
西遼河を起源とするトランスユーラシア言語が日本語の起源であるとする学説が、2021年に発表された。
しかし、2022年に多くの学者から、その学説を撤回するよう要望が出された。
まず、その学説の基となったと思われる2冊の著作を論評する。
後半では、学説の問題点を洗い出す。
<1 解説>動画あり
- 1-1 学説の元となった書籍「古代日本と朝鮮半島の交流史」(西谷正)
-
- 旧石器時代から、人、石器、原始農業、土器、墓制、住宅、環濠集落とも朝鮮半島から日本に一方的に伝播したと主張
- 氷河期でも朝鮮半島と日本は陸続きではなかったことが踏まえられていないうえ、主張が一方的
- 1-2 学説の元となった書籍「農耕の起源を探るーイネの来た道」(宮本一夫)
-
- 日本への稲作は、南方からでもなく、中国・江南からでもなく、大陸経由朝鮮半島から伝播ルートのみと主張
- 各伝播ルートの検証が不十分なうえ、日本から朝鮮半島に伝播した出土物が無視されている
- 1-3 西遼河起源説とは
-
- 言語的・考古学的・遺伝的根拠(多角的であることから三角測量と呼称)をもとに、西遼河を起源とするトランスユーラシア語が、日本語の起源であるとする説
- 2021年にドイツ等の国際チームがネイチャー誌に発表。日本の研究者も名を連ね、毎日新聞が大きく報道
- 1-4 同説の問題点
-
- データセットは開示されており検証ができるが、根拠が不明瞭。
- 1-5 同説への反論
-
- 仏言語学者トマ・ペラール氏が来日し反論すべきとセミナー開催
- 言語学的問題点 言語間で共通する単語はわずかしかない
- 遺伝学的問題点 日本人と韓国人の遺伝的形成モデリングが内部矛盾している
- 考古学的問題点 遺跡の系統樹の根拠が不明
以上により論文撤回を勧奨
<2 質疑応答>
- 2-1 Q 氷河期には朝鮮半島との間に陸橋があったと考える
- A 半島と対馬の間に幅10km以上の水路があったことが最新研究で確定
- 2-2 Q 朝鮮半島南部と日本は国境がないので同じ文化圏とみるべき
- Q 日本と朝鮮と分けて考えるべきではない。日本人とか弥生人とは根拠が不明
動画と資料
- ➤ 動画 YouTube 動画リンク
-
-
「西遼河起源説とその撤回要請及び朝鮮半島と日本に関する2冊の書籍:論評」 丸地三郎 133
分
https://youtu.be/Qa2ds9LNbYc
-
「西遼河起源説とその撤回要請及び朝鮮半島と日本に関する2冊の書籍:論評」 丸地三郎 133
分
- ➤ 資料
-
- 「西遼河起源説とその撤回要請及び朝鮮半島と日本に関する2冊の書籍:論評」 丸地三郎 PDF約 5.3MB
-
「最終氷河期の対馬海峡関連の論文」 丸地三郎 PDF約1.25MB(2023/09/25 追加)
☆ 論文リスト- 大場忠道 著「海水準変化に関するコメント」 1988年 第四紀研究
- 大嶋和雄 著「第四紀後期の海峡形成史」 1990年8月 第四紀研究
- 多田隆治 著「最終氷期以降の日本海および周辺域の環境変遷」 1997年12月 第四紀研究
- 菅浩伸 著「東アジアにおける最終氷期最盛期から完新世初期の海洋古環境」2004岡山大
- 中川和哉 著「後期旧石器時代における日本と朝鮮半島」 京都府埋蔵物文化財論集第7 中川:調査第2係長
- 英文論文「最終氷期の海面変動と朝鮮(対馬)海峡の古地理」 著者S・パーク、 D・ユ 2000年9月刊
- 河村善也 著「第四紀における日本列島への哺乳類の移動」
34.「天孫降臨と史実の関係」(2023年10月7日)
2023年10月7日 34回 古代史を解明する会「天孫降臨と史実の関係」は、13:00よりオンライン開催された。出席者12名。
- テーマ
- 「天孫降臨と史実の関係」
天孫降臨に関して、古事記/日本書紀の本文及び複数の一書の記述内容の違いを一覧表とし、参加者に配布。
記紀のニニギの天孫降臨に関する記述と史実は、どのような関係にあるのか。ニニギはどこに降臨したのか? 3人の発表者がそれぞれの見解を述べ、その後質疑応答がなされた。
その他に、前回の33回 「西遼河起源説・・・・」(2023年9月9日)での質疑の行われた「最終氷河期の対馬海峡」に対する補足説明もなされた。
<構成>
- 伊藤雅文氏による動画とワード資料を用いた解説
- 清水徹朗氏によるPPTを用いた解説
- 可児俊信氏によるPPTを用いた解説
- 質疑応答
- 丸地三郎氏による「最終氷河期の対馬海峡」に関する補足説明
<解説と質疑応答>
- 伊藤雅文氏による解説(動画あり)
- 日本書紀には、ヤマトはオオナムチ、ニギハヤヒ、神武天皇の順に支配されていたことを伺わせる記述がある。
- 書紀では、アメノホヒ他国譲り後2人が派遣されるが,いずれも復命しない。アメノホヒの子がニギハヤヒであり、オオナムチを討伐し、次にヤマトに降臨した。これも天孫降臨である。
- 九州に天孫降臨したニニギの子であるヒコホホデミ(=神武天皇)が神武東征し、天皇の系譜となったためニギハヤヒの天孫降臨は記紀に記載されていない。
- ニニギは高天原が討伐した狗奴国に天孫降臨した。
- 清水徹朗氏による解説(動画あり)
- 宝賀寿男著「天皇氏族-天孫族の来た道」を紹介。
- 天皇氏族には天孫族、物部氏、宇佐氏等の流れがある。
- スサノオは韓族でイソタケルと同一神。八幡神もイソタケル。
- 崇神が実在の最初の天皇。応神天皇から王統が変わった。
- 息長氏族は宇佐国造の支流である。
- イソタケルが始祖の天孫族(神武を祖とする皇統と同族)であり、広い意味で邪馬台国以降は万世一系。
- 可児俊信氏による解説(動画あり)
- スサノオの出雲族統一(ヤマタノオロチ退治)後、北部九州を侵略し、天孫族を支配下に置く。
- スサノオの死後、オオナムチが後継者となるが、次第に天孫族が失地を回復。奪回地に降り立ったのがニニギの天孫降臨。
- オシホミミが本来の降臨者だったが、早世したため急遽ニニギが降臨。
- オオナムチとヤマトのニギハヤヒの死後、天孫族は出雲を攻略(国譲り)。
- 日向三代は実は三兄弟を改ざんしたもの。その理由は持統天皇の即位を正当化するために、アマテラスの孫のニニギが降臨したことにした。
- 質疑応答
- 伊藤氏:記紀は系譜を操作して、架空の世代を造り、世代数を引き延ばしている。
- 葦原中つ国の場所 伊藤氏:高天原(北部九州)より以東・以南 可児氏:九州とヤマトの間の場所。
- 天孫降臨を裏付ける証拠 可児:スサノオから神武まで100年という短い期間(2世紀後半~3世紀前半)であり考古学的な証憑はない(しいていえば倭国大乱=出雲族の北部九州侵攻か) 伊藤氏:初代天皇が日向にいた期間は短い等、説を裏付ける考古学的証憑はない(ただし初代天皇即位は301年)。
- 天孫降臨の前に国譲りがある 伊藤氏:国譲りの前にニギハヤヒの天孫降臨があった。それは記紀にかかれず、国譲りの後のニニギの天孫降臨が記紀に書かれた。
- 後漢書の倭国朝献/金印(AD57年/AD107年)や魏志倭人伝(張政の来日AD248年)と自説との関係 伊藤氏:記紀はこれらより後のこと。纏向は垂仁以降の代の遺跡。可児氏:金印とかの時代は北部九州の小国分立時代の話なので記紀にのらない。
- 丸地三郎氏による「最終氷河期の対馬海峡」に論文紹介と補足説明(動画あり)
- 33回の会で最終氷河期でも対馬海峡は水路があったと報告したが、陸橋になっていたのではないかという疑問がでたため、資料を追加し、報告した。
- 1984年に有孔虫の殻の分析から水路があったと論文が出た。この論文への別の方法論からの論議が行われ、ほぼ水路があったと議論になった。2000年に海峡の海底を測量・計測し、水路があったことを確認し最終決着した。
- 古代に地図から、黄河・長江(揚子江)の河口の位置を推定し、産総研の「海面上昇シミュレーション」地図で、流路を推定した。黄河と長江が途中で合流し、海面が90m以下に下がった時代は、河口が、対馬海峡に近い、済州島の北側になったと推測される。
- 海面が130m下がった場合も、流量の多い長江から、淡水が対馬海峡に流れ込んだと考えられる。
- 次に、水路の水が浅い部分は淡水、深層部は海水と推定された。
動画と資料
- ➤ 動画 YouTube 動画リンク
-
-
「天孫降臨と史実の関係 1」伊藤雅文氏 19分
https://youtu.be/rwCkDCgqCJ8 -
「天孫降臨と史実の関係 2」清水徹朗氏 29分
https://youtu.be/H3Gw5efT8wc -
「天孫降臨と史実の関係 3」可児俊信氏 30分
https://youtu.be/bXZeA5C_-6Y -
「最終氷河期の対馬海峡」 丸地三郎氏 28分
https://youtu.be/aRJ9ZSlKpfY
-
「天孫降臨と史実の関係 1」伊藤雅文氏 19分
- ➤ 資料
-
- 記紀異伝比較(天孫降臨) 可児俊信外 PDF 591KB
- 「『日本書紀』が書かなかった天孫降臨」伊藤雅文氏 PDF176KB
- 「『日本書紀』が書いた瓊瓊杵尊の天孫降臨」伊藤雅文氏 PDF約90KB
- 「宝賀寿男の天孫族起源論」清水徹朗氏 PDF約2MB
- 「天孫降臨と史実の関係」可児俊信氏 PDF 約2MB
- 「最終氷河期の対馬海峡」丸地三郎氏 PDF 約5MB
35.「邪馬台国と高天原の関係」(2023年11月11日)
2023年11月11日、35回古代史を解明する会「邪馬台国と高天原の関係」は、13:00よりオンライン開催された。出席者9名
- <テーマ>
- 「邪馬台国と高天原の関係」
- 魏志倭人伝に記載された邪馬台国は、古事記・日本書紀に記載されていない。
- 魏志倭人伝の邪馬台国と記紀の高天原の関係はどうなっているか?
- 邪馬台国=高天原か? 若しそうであれば、卑弥呼と天照大神も同一人の可能性がある。
レポート内容
- <構成>
-
- 可児俊信氏によるPPTを用いた解説
- 質疑応答
- 丸地三郎氏によるPPTを用いたコメント
-
可児俊信氏によるPPTを用いた解説
- 考古学で北部九州にクニが存在していたことが明らか(天孫族のクニ)。天孫族のクニの史実を改竄したものが記紀の高天原。
- 改竄した背景は、記紀作成時期は、天武朝で皇親政治が行われた時期。天皇が神の子孫であり、他の豪族より上であり、出雲族との抗争はなかったこととしたいため。出雲族の系譜の改竄、神社の祭神の改竄も行われた。 よって更新世日本書紀には、ヤマトはオオナムチ、ニギハヤヒ、神武天皇の順に支配されていたことを伺わせる記述がある。よって天孫族のクニ=高天原。
- 天孫族のクニを邪馬台国とみなして、主要人物の生存期間を配置しても矛盾しない。よって天孫族のクニ=邪馬台国。よって高天原=高天原邪馬台国となる。
- よって卑弥呼=天照大神となる。
- 質疑応答
- 多久と甘木を合成して高天原の名となった。
- ヒコホホデミ(301年神武として即位)から1世代25年として遡るとアマテラスは175年生となり、卑弥呼の世代と一致する。よってアマテラス=卑弥呼。
- 魏志倭人伝の記述をふまえるべき。高地性集落等の考古学を見ると西から東に移動しているはず。
- 出雲と北部九州は古くからつながりがあった。銅鐸等をもとに出雲文化圏があったとはいいがたい。
- 銅剣・銅矛は北九州発祥。西から東に文化等は移っているので出雲から北部九州への動きは考えがたい。
- 初婚年齢を15歳とするのは早いのでは。男性は20歳位では?
- 出雲から鉄が出ない。考古学の知見を踏まえて欲しい。基本は北部九州なので一時だけ出雲というのはどうか?
- 丸地三郎氏によるPPTを用いたコメント
- 天孫族と出雲支配下全体での鉄の量はほぼ同等であり、出雲が支配したとは考えにくい。工業生産力は天孫族が上回る。
- 梁書の記述は信頼できないので、倭国大乱の時期の根拠とすべきではない。
- 主要人物の生存期間表にも矛盾が見られるのでさらに精査すべき。
動画と資料
- ➤ 動画 YouTube 動画リンク
-
- 「邪馬台国と高天原の関係」可児俊信氏 63分
https://youtu.be/4p7ve6nNrgc - 「邪馬台国と高天原の関係:可児説へのコメント」丸地三郎氏 27分
https://youtu.be/NrJHI0OQM-w
- 「邪馬台国と高天原の関係」可児俊信氏 63分
- ➤ 資料
-
- 「邪馬台国と高天原の関係」 可児俊信氏 PDF 3.8MB
- 「丸地氏のコメント」 丸地三郎氏 PDF 3.5MB
36.「日向三代の記述の理由」(2023年12月9日)
2023年12月9日、36回古代史を解明する会「日向三代の記述の理由」は、13:00よりオンライン開催された。出席者8名
- <テーマ>
-
「日向三代の記述の理由」
記紀の日向三代の記述は何のために書かれたのか? それを6つの疑問を解くことで解明していきます。
- 天孫降臨し、邇邇芸命の結婚相手を見つけた場所は何処か?
- 真床追衾・真床覆衾(まとこおうふすま)とは何か?
- 天孫降臨の時期は、何時か? 出雲国譲りの後か? 天岩戸事件の後か?
- 天孫降臨に参加して人の規模は?
- 記述の理由は?
- 日向三代の場所を知るには、どんな証拠が有るのか?
- <構成>
-
- 丸地三郎氏によるPPTを用いた解説
- 質疑応答
1 解説
- 日向三代のあらすじ解説
- 6つの疑問
2 質疑応答
- 論点を複数提示
- オオヤマツミが何者かを知ることが手がかりになる。
- オオヤマツミは記紀の各所に登場するので不思議である。
- 天孫降臨した場所は北部九州だが、結婚したのは鹿児島付近で、時間もかなり後のことである。
- 海幸彦,山幸彦の争いは後継者争いである。よってやぶれた海幸彦は本拠地を離れ鹿児島へ向かった。よって本拠地は鹿児島ではないことになる。オオヤマツミも北部九州ということになる。
- 記紀は政治都合で書かれているが何から何まで作り話ではないはず。
- 神話のうち、空から降りてくるのは北方系、海から来るのが南方系。記紀は北方系。
- 北部九州の遺跡には三種の神器の原型がある。纏向にはない。
- ニニギは北部九州が他の国から攻められて南九州に亡命した。
- 天孫降臨は中国の呉からの亡命である。
- 古事記の注では、岩戸事件の後に天孫降臨が続いていたと解釈されている。
- 墓を研究すると、史実の裏付けが得られる可能性がある。
- 古代国は中国に生口を移送したり古墳をつくったりで経済力はあったのではないか
3 次回
- 考古資料と対応付けることで明確になる可能性があるので、丸地がその発表を行う。
動画と資料
- ➤ 動画 YouTube 動画リンク
-
- 「日向三代の記述の理由」 129分
https://youtu.be/9U3NRAa7UQQ
- 「日向三代の記述の理由」 129分
- ➤ 資料
-
- 「日向三代の記述の理由」 丸地三郎氏 PDF 1.8MB
37.「文献と考古資料の対応:天孫降臨・日向三代」(2024年1月13日)
2024年1月13日13:00よりオンライン開催された。出席者10名
- テーマ
- 「文献と考古資料の対応:天孫降臨・日向三代」
- 前回、記紀の歴史的解釈を試みて発表を行い、参加者と議論を交わしたが、年代/地理の解釈が大きく分かれ、集約されなかった。
- そこで、記紀の記した歴史と、考古資料・中国史書と対比を行うことにした。
- 記紀から古代史を復元する試みを行った。
- さらに復元古代史を考古学等の研究知見で裏付けるという困難な作業を試行した。
- その結果、復元古代史が考古学等の知見とよく一致することが判明した。
- <構成>
-
- 丸地三郎氏によるPPTを用いた解説
- 次回は、この解説に対しての討論を行う。
1 解説
- <前回(第36回)の振り返り>
-
- 記紀での天孫降臨・日向三代のあらすじの確認
- 前回での参加者からの意見のまとめ(意見が分かれる箇所、概ね一致する箇所)
- <記紀から復元した真の古代史>
-
- ウケイ→天岩戸事件→スサノオ追放→天孫降臨→ニニギの結婚→日向三代→国譲り→神武東征の順で、記紀を復元
- アマテラスとスサノオの天孫族内の争いでスサノオが一旦勝利するが、アマテラスが逆襲し、スサノオは出雲へ追放
- スサノオ(またはその後裔の)出雲族が天孫族を再度侵略。アマテラスの後継者のオシホミミが福岡平野で敗れ、ニニギを後継として、イト国へ脱出
- イト国で力を蓄えた天孫族はウガヤフキアエズの代になって出雲族を撃破して放逐
- 引き続き出雲本国を征服
- 天孫族だったニギハヤヒがヤマトを占領してしまったので、イツセが東征した(イツセは戦死したので神武が引き継ぎ、初代天皇となった
- <復元古代史と考古学等知見での裏付け>
-
- 王墓、青銅祭器、土器、戦傷遺跡、甕棺、高地性集落の考古学知見と復元古代史をすりあわせ
- 福岡平野、須玖岡本、糸島の遺跡とその付近の戦傷遺跡の時代変遷が復元古代史と一致することを確認
- 三種の神器のある王墓が天孫族のいた場所とみなすと、これもよく一致
- 青銅祭器、甕棺の分布も復元古代史と一致
動画と資料
- ➤ 動画 YouTube 動画リンク
-
-
「文献と考古資料の対応:天孫降臨・日向三代」 163分
https://www.youtube.com/watch?v=oWKcaIwwjF8
-
「文献と考古資料の対応:天孫降臨・日向三代」 163分
- ➤ 資料
-
- 「文献と考古資料の対応:天孫降臨・日向三代」丸地三郎氏 PDF 9.2MB