年輪検証の意見交換コーナー
最終更新日:2025/08/23
当ページは「年輪年代測定法に関するデータ公開」のページを踏まえての意見交換のためのものです。
年輪年代法のデータそのもの、解析ソフト Past の入手方法などについては、
「年輪年代測定法に関するデータ公開」
のページ
のページ
● 目次を表示/非表示
- はじめに
- 解析ソフトPast の入手方法
- 形式の違うサンプルデータの紹介
- 開示された標準曲線パターンとその構築データ
- 暦年標準Aパターン(1009年~1984年)
- 暦年標準Dパターン(512年~1322年)
- 暦年標準Eパターン(紀元前37年~838年)
- 暦年標準Fパターン(紀元前317年~257年)
- 木曽ヒノキ暦年標準パターン(紀元前705年~2005年)
- 埋木15点年輪パターン(紀元前912年~紀元前94年)
- 「補足」暦年標準パターン(紀元前447年~257年)
- 開示された年代測定データ(試料年輪データと暦年標準パターン名称)
をご覧下さい。
運用ルールについて
奈文研からの公開年輪データを検証してみてのコメントを募集いたします。
- コメントはメールにて題名を「検証に関するコメント」としてお願いいたします。
- コメント者のお名前、メールアドレスは表示せず、「発言1」「発言2」...となります。
- コメントに対する意見は、コメント先番号付でメール頂ければ、「発言1-1」「発言1-2」...といたします。
- 中傷・誹謗となるコメント、意見は掲載いたしません。
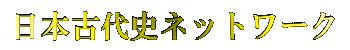
コメント
早速、Past 5.2.1をインストールし、データを一個だけダウンロードし、4列目を選んで、単純にグラフで描画してみました。
これからアプリケーションの使い方を覚えていろいろデータを見ていきたいです。30年近く諦めていた願いが叶い、夢のようです。
勉強にはまだまだ時間がかかると思いますが、腰を据えて取り組めば、いろいろ見えてきそうです。
武田春樹さんが、ユーチューブで動画を発信しましたので、お知らせします。
古荘英雄さんの対談会ライブが開催されました。
(日本古代史ネットの特別会員の方々には、事前にご案内をいたしました。)
{ライブは終わりましたが、今も見ることができます。}
ライブ配信で使用された資料「年輪年代法の基礎データで遊ぶ」2025年06月22日(武田春樹さん作成のPDF資料)は、こちらのURLから見ることができます。
➥年輪年代武田.pdf
年輪年代法のデータを使い、纒向石塚出土の板材の検討した結果がユーチューブで語られています。
最後にとんでもない映像が流れますが、ご容赦を!
年輪データ公開へのご尽力をありがとうございます。
早速、私の方でも検証を試行してみましたが、単純な相関ではうまくいかないことが判明しました。
調べてみると、その理由は樹木の年輪幅 (Ring Width, RW) には 「樹齢に伴う長期減衰トレンド」 と 「気候など外部要因による年々の振動成分」 が重なって入っていることに対し、年輪年代法(クロスデーティング)が狙うのは 後者=気候シグナルの同期 であって、前者がノイズになって疑似相関が起きているためだと判明しました。
そのため、研究では樹齢トレンドを取り除き、年々変動だけを取り出した「リング幅指標 (Ring-Width Index, RWI)」 を作った上で相関や t 値(Baillie & Pilcher tBP)・GLK (Gleichläufigkeit) を計算しての検定が行われるそうです。
この樹齢トレンドを取り除くデトレンド処理が曲者で、複数の方法を試行してみましたが、うまく取り除けないようで、年輪年代法はこのデトレンド処理に非常に強く依存することがわかりました。
著名なクロスデーティングプログラムのCOFECHAで行われている手法を参考にデトレンド処理を実装したところ、うまく樹齢トレンドを取り除けたようで、法隆寺五重塔心柱では 591 年、纏向石塚古墳では 171 年という、ほぼ奈文研の推定と一致する結果が得られましたので、プログラムおよび結果をお送りします。
プログラムは python の Jupyter Notebook で記述しており、パブリックドメインに公開します。改造等はご自由にどうぞ。
誤記があったため、訂正させてください。
「纏向石塚古墳では 174 年」の誤記でした。プログラムも差し替えをお願いします。
日本古代史ネットワークのスタッフです。一括で ZIP ファイルとしてダウンロードできるように致しました。解凍の上ご利用ください。纏向関係のファイル2点は修正版に差し替え済です。
➥ダウンロード:COFECHA検証.ZIP
圧縮解凍ソフトや Windows 自体の文字コード UTF-8 への対応が不完全なため、ファイル名中の漢字などの2バイト文字が解凍時に文字化けすることがあります。
図が有りますが、
何故、前半部分が無いのでしょうか? 前半部分が、纏向石塚古墳板材と対比され、一致する部分と思います。
お教え頂けると幸いです。
ご質問ありがとうございます。
以下にてご回答いたしますので、よろしくお願いいたします。
----
年輪年代法では、*年代のずれを変えながら相関を計算*しますが、
が一致年代の評価で重視されます。
このプログラムでは相関の信頼性を検証する方法として、統計学で定番のt検定という方法を使っています。t検定では、その値 tBP が 3.5 を大きく超えていると、この相関は「有意である」(偶然ではない)と評価します。
纏向石塚古墳のサンプルでは、174 年にて tBP が 3.5 を大きく超えていますので、これは有意な相関だと言えます。
加えて、異なる樹木の年輪では気候変化に対する年輪幅の絶対値や比率までが一致するわけではないので、ピアソンの相関係数や tBP では相関がうまく出ない傾向があり、年輪年代法では GLK(Gleichlaufigkeit)では年輪幅が前の年よりも「増えた/減った」という変化の方向だけを抽出して相関を取る検定方法も併用するのだそうです。
この GLK 値は、数学的にはランダムなデータ間で相関係数が 0.5 となるのですが、 経験的にそれが 0.6 を超えると偶然の一致よりも「構造的な一致」があると推定されるため、一般的に「有意である」と評価するのだそうです。 0.6 を「中程度の信頼性」、0.7 以上を「高い信頼性」と見なすこともあるようです。
纏向石塚古墳のサンプルでは、174 年にて GLK も 約 0.65 の相関を示していますので、中程度以上の相関にて有意な相関だと言えます。
これら、t検定の結果とGLK検定の結果を併せ 174 年と推定しました。
暦年標準Eパターンのデータが -37 年から始まるのに対し、本評価での図の左端が162年からとなっているのは、纏向石塚古墳のサンプルの外周200年分との相関を取っているからです。纏向石塚古墳のサンプルの外周200年分と暦年標準Eパターンの -37~162 年までの内周200年分との相関が初年となり、以降、暦年標準Eパターンを1年ずつ外周側にシフトしながら200年分の相関を取っていますので、これは部分的な相関による偶然の一致ではありません。
纏向石塚古墳のサンプルの元データは245年分の年輪ですが、この全ての相関を取ると開始年が207年からになって170年代の相関がわからなかったので、最初に外周200年分を切り出して公平に162~834年までの相関を取りました。
法隆寺五重塔心柱のサンプルの方が相関が綺麗に出ていますが、こちらも同様に tBP 3.5, GLK 0.6 を同時に満たすことから、591年と推定しました。
丁寧なご回答を頂き、有難うございます。
● 先に、折れ線グラフ3種の横軸(年代)の質問の件
長期間の年輪幅を持つ試料と比べる場合には、暦年標準パターンのカバーしている範囲の両端に近い箇所では、原理的に、比較できないことを理解しました。実際に、対比作業の経験があれば、直ぐに理解できる筈のことでした。了解しました。
● 折れ線グラフ3種から「纏向石塚古墳のサンプルでは、174 年」と判断した理由についての質問の件
3種類の算出方法の結果をグラフに表し、各々の評価基準が、ご回答で、判りました。
『GLK (Gleichlaufigkeit) では年輪幅が前の年よりも「増えた/減った」という変化の方向だけを抽出て相関を取る検定方法も併用する』この方法まで既に利用されていることに、驚きました。
最初のご発言にあった、
をやっと理解いたしました。
スレッド主さんの再検証作業で、法隆寺五重塔と纏向石塚古墳板材に関しては、暦年標準パターン E と対比した結果、光谷氏の測定結果とほぼ同一の結果となった。このように理解して間違いないでしょうか?
私の結論から申し上げると、あくまでも中立的に科学的に検証を行った結果、法隆寺五重塔と纏向石塚古墳板材に関しては、「奈文研による推定は、学会で標準的な計算手法によって適切に推定した妥当な結果である(恣意的な操作や改竄は無い)」ことを確認した、までです。
一方で、年輪年代法はデトレンド処理に非常に強く依存することを理解しましたので、「この年代が絶対的に正しい」、「奈文研による推定を支持する」とまでは思っていません。
理由を記す前に、私の立場・背景をご説明させてください。
私、某企業でAIの研究開発を行っている者で、博士号も保有している元研究者です。
よって、古代史や年輪年代法に関しては専門外の一般人ですが、中立的に学術的に検証を行うことに関しては博士としての責任を自負しており、不公平・不適切な方法での検証は行いません。
一方で、趣味では日本古代史を理系研究者の視点から探求しており、日本の史学会の定説に対しては様々な疑問・異論を持っています。
例えば文献に記された年代と年輪年代法で推定した年代が合わない「法隆寺五重塔心柱」に対し、「100年寝かせた」という珍解釈が定説になっているらしいことに対しては、理系の学会では有り得ない状態だと呆れています。
その上で、内心では疑いの念を持ちつつも、博士として中立的に学術的に検証を行った結果、確かに適切に推定した妥当な結果である(恣意的な操作や改竄は無い)と、確認しました。
ただし、異分野の理系研究者の視点から見て、デトレンド処理に非常に強く依存する年輪年代法には危うさを感じましたので、年輪年代法による推定結果は「絶対的に正しい」とまで鵜呑みにすべきではなく、あくまでも年代を比定する根拠の1つに過ぎないと捉えるべきだと感じています。
炭素年代測定法や分子人類学も類似ですが、史学会では測定法を理解して検証できる方が非常に少ないためか、結果を絶対に正しい「科学的な値」として扱われているのには、非常に危険を感じます。
以上、長文となり失礼しました。
ご回答、有難うございます。
とのこと。了解いたしました。
年輪年代法論争の論点として、一番気になる処は、暦年標準パターンが適切なものか? です。
特に、暦年標準パターンEを使って年代を特定された事例に関して、疑問が出されています。
今回7種類の暦年標準パターンの基本データが公開されましたが、暦年標準パターンEについて調べることができれば有難いと思っています。
良い知恵は無いでしょうか?
ご自身の立場・背景をご紹介頂き、有難うございます。
不思議と思っていた部分が、クリアになってきました。
この件、共感いたします。
昨晩、寝る前に専門の方のコメントに気づき、早速、今朝、出勤前にプログラムをダウンロードし、いろいろ試してみたのでご報告します。
専門家の方の見解を待ち、それを見てから自分の考えをまとめようとのんびり構えていた矢先、こんなにも早くに専門家の意見が出てくるとは思ってもいませんでした。
年輪が一致する箇所と一致しない箇所があると私は考えていたので、今回、プログラムを使って、その一致しない箇所を検証することができました。
纒向石塚古墳の板材は年輪の最初の30年と終わりの30年に強く相関する箇所があり、それ以外の部分については果たして大丈夫なのだろうかと私自身、確信がもてなかったのですが、一致する最初と終わりの30年ずつを削り取り、200年ではなく100年程度の幅にしてプログラムを動かすと、最も一致する場所とは言えなくなるものの、偶然ではないレベルでの一致が見られたので暦年標準パターンEは一応正しいと認識しました。
暦年標準パターンEと木曽ヒノキですらあまり一致しないという私の予想についても確認しました。
木曽ヒノキの暦年パターンから纒向石塚古墳の木材相当の部分を切り抜き、プログラムで確認しました。
やはり、唯一の一致箇所ではなくなるように見えるので、暦年標準パターン同士でそれほど一致しないという予想は当たっているのかも知れません。
ただ、ある程度、年代を絞って年輪年代法を運用する限り、問題はないのかも知れません。
デトレンドについては専門家の方同様、私も危うさを感じています。
強いデトレンドというのは、樹齢に伴なう長期トレンドの除去を通り越し、悪く言えば、信号をなまらせて無理やり相関度を高めているといった部分もあるように思います。
また、樹齢に伴なう長期トレンドをとっぱらうレベルのデトレンドではそれほど相関度は高くならないのも事実だと思います。
実際、いくつか試したのですが、Past に付いている機能くらいでは相関度を極端に高めることはできませんでした。
なお、私自身、結果が出るなら強めのデトレンドもありかとは見ていますが、ただ、弊害として、相関していない箇所での誤一致の可能性が高まるという点については懸念しています。
私が危ういと思うはその部分にあります。それは暦年標準パターンを作る時にも当てはまることなので。
木曽ヒノキの暦年標準パターンでも、纒向石塚古墳の板材についてプログラムで見ました。然るべきところで一致していました。むしろこっちの方が一致しているように見えます。
二つの暦年標準パターンで一致することは偶然ではあり得ないという点から考えると、現在公開しているデータは正しいと言わざるを得ないです。
ただ、年輪年代法で分かることはあくまでも伐採年であり、年代というのは総合的な判断が必要なものだから、年輪年代法の結果が即遺跡の年代には成り得ず、あくまでも有効なデータの一つと私は考えます。
しかし、今回のデータ公開によってはじめて年輪年代法の結果は、有効なデータとして認められる存在になったと私は考えます。もっとも、この世に絶対はないので、常に我々はデータを検証するという習慣を持たないといけないのかも知れません。もちろんそれは年輪年代法に限らずですが。
専門家の方の結果は私の結果と1年ずれています。たぶん、紀元前37年を-37年としているためかなと思います。紀元前37年は-36年なので。今朝、プログラムを見たばかりで自信はありませんが。
ようやく、私の中でかなりすっきりした気がします。プログラムを公開してくれた専門家の方にも感謝です。
デトレンドの手法については、プログラムを見ながら、これから勉強していきたいです。
スレッド主さんは、「COFECHA検証」を読まれて、多分、大変ビックリされ、興奮されたのかと思います。時間を忘れて、ご自分で、追加の作業をしたのではないかと想像します。
私も、スレッド主さんに、こんなすごい話が来てますが、どう思われますかと聞いてみようかと思いましたが、止めていました。ご連絡した方が良かったようですネ。
非常に興味深い追加確認の作業をやられたと思い、見ています。
スレッド主さんにお願いが有ります。
追加作業をやられていくつかの事実が判ったのかと思いますが、もう少し、事実関係を私達にも教えて下さい。
例えば、
この箇所ですが、COFECHA検証プログラムを利用して、何回かの作業を行い確認されたのだと想像します。
などなどが有るのかと思います。
お手数ですが、個々の作業の条件と結果を、お知らせ下さい。
ご本人に確認してみます。
有難うございます。
素人がお試しでやったことなので、お恥ずかしい検証ですが、ご説明いたします。
纒向石塚古墳板材と暦年標準パータンEとの照合において年輪が一致する箇所と一致しない箇所がある件について
纒向石塚古墳板材の年輪は246年あります。この246年間において暦年標準パータンEと一致しているように見える箇所と一致していないように見える箇所があることに気づきました。
そこで纒向石塚古墳板材と暦年標準パターンEが重なる紀元前37年から紀元後175年までの相関係数を紀元前37年から25年間の相関係数、紀元前36年から25年間の相関係数といった具合に1年ずつずらしながら確認しました。
25年という年輪幅は短すぎるのですが、傾向を見たかっただけなのでこれで確かめました。
結果は、予想どおり、どの25年間で見るかによって相関係数が大きく異なることが分かりました。
添付の画像1です。
紀元後25年頃や148年頃は高く相関するも紀元後41年頃や116年頃は殆ど相関しない、そんな結果でした。
年輪が高く相関する箇所については正しいとして、相関しない箇所については、暦年標準パターンEに誤った年輪が混ざっていないか、そういったあたりを懸念しました。
ただ、適切なデトレンド処理を見つけていなかったので、調査を中断して専門家の方の意見が出るのを待っていたところ、早くに検証プログラムが公開されました。
纒向石塚古墳板材の外側の年輪を30年分削除し、検証の年輪数を200年から100年に変更しました。
これにより纒向石塚古墳板材の年輪が紀元後45年から145年となり、極めて高く相関する紀元後25年頃や148年頃が省かれたことになります。
このほとんど相関しない部分を含む箇所が適切なデトレンド処理でも月並みの相関しかしないなら、暦年標準パターンEのこの区間は怪しい。
適切なデトレンド処理により、そこそこ高い相関を示すなら、暦年標準パターンEのこの区間は決して出鱈目ではない。
そう予想しました。
検証プログラムで試した結果、外側175年から30年削った145年のところで偶然ではないレベルでの一致が見られたので、暦年標準パターンEは、ノイズなどによってあまり一致しない箇所があるものの、繋ぎ間違いのようなものはないと判断しました。
添付の画像2です。
早速、検証の内容をお知らせ頂き、有難うございます。
纒向石塚古墳板材とパターンEの対比と、パターンEの確認を読ませて頂きましたが、私が適切にスレッド主さんのやった作業を理解できたか、心配な面も有りますが、理解した限りでは、作業に不都合な点があり、結論が正しく出せていないように思えます。
説明には図が必要そうですので、添付のワード文書(別発言として転載)にしました。ご覧ください。
検証していく作業は、中々難しいことが多いと思います。
手順や作業内容を明確にして、皆さんの行う一つ一つの作業を積み重ねられるようにして行きたいと思います。
宜しくどうぞ、お願い申し上げます。
尚、3.暦年標準パターンEと木曽ヒノキ 以降の内容に付いても、作業内容と結果が判るようにして頂けると、幸いです。
手順を具体的に示して頂き、有難うございます。
纒向石塚の板材と暦年標準パターンEの照合に関して、部分的照合を行い相関関係を確認されたこと、大変興味深く、見させて頂きました。
スレッド主さんの記述を正しく理解できたか、良く分かりませんが、私が理解できた限りでは、手順/作業に納得の行かないことと、その手順から考えると、との結論に疑問を持ちました。
事前の確認で、25年間分の幅で、パターンEと相関関係が高い部分と低い部分の箇所を調べ、AD25年頃とAD148年頃では高い相関を持つ。
相関の高くない部分で、パターンEとの相関をCOFECHA検証で調べ直すと、パターンEの特性が判るのではと、作業をしてみた。
纒向石塚の板材の「紀元後45年から145年」の100年間分の年輪幅データを使って、(極めて高く相関する部分を省いて、)パターンEとの相関を調べた。
私が図を使い確認したとこと、調べた100年間の中には、極めて高い相関関係を持つ部分は148年~123年の25年間あり、このうちの22年分が、100年間に入る。
グラフを見ると148年以前の4-5年間も高い相関性を持つため、22年間プラス数年間は、極めて高い相関性を持つ部分を含むことになった。
従って、COFECHA検証の結果のグラフを見ても、tBPの値は、基準の3.5には、全然達していない。GLKの値は、相関性の高い部分が貢献し、基準の0.6以上となっているが、145年以外の箇所にも高い数値が有り、相関性が高いとは、云えないと私には見える。再検討頂きたい処です。
お世話になります。
貴殿のプログラムと結果をホームページで見た人から、ご指摘が有りました。
とのことです。
如何でしょうか?
おや、そうなのですね。知りませんでした。
ご指摘の通り、初期値を-37としているので、1年少ない値にずれています。
start_year_known = -37 ← ここを -36 に修正して下さい。
ご指摘をありがとうございます。
1年の差異がでることを、専門家の方に確認してみました。
スレッド主さんのご指摘の通りでした。
有難うございます。
ご確認ありがとうございます。ご指摘のこと、思い当たります。お手数をおかけし、申し訳ありません。
帰宅後、再度、やり直してみました。結論は大きく変わらないのですが、私がやりたかったことに近づいたと思います。
相関係数0.4以上は強い相関があるとされており、遡ると西暦129年~153年から0.4を満たないため、西暦146年以降を削るのではなく、西暦130年以降を削る方が武田が意図することとなります。
となると、西暦30年~129年の100年を区間にすべきですが、前半での極めて高い相関を持つ箇所が西暦34年まで続くため、そのことを考慮すると西暦35年~129年の95年間が極めて高い相関関係を持つ部分を削った区間となります。
暦年標準パターンEと纒向石塚古墳板材の重なる年輪のうち、敢えて極めて高い相関を示す箇所を削った西暦35年~129年の95年間の年輪を用いてグラフを作成した結果は添付のとおりです。
この場合でも西暦129年を検出できているため、暦年標準パターンEと纒向石塚古墳板材の重なる年輪のうち、極めて高い相関を示す部分だけでなく、その狭間にある箇所も、決して出鱈目な年輪ではないと判断しました。
まだ、いろいろと不安が残りますが今の到達点としてはこんなところです。
暦年標準パターンEと木曽ヒノキとの相関については、また、手順などをまとめたいと思います。
いろいろお手数をおかけします。
色々とお手数を掛けます。
検証に関しては、明確なデータで行うべきと思っていますので、うるさく言って済みません。
やり直して頂いたのですが、まだ、納得の行か居ない箇所があります。
下記の部分についての私の理解が違っていたことを認識しました。
正しい理解では、相関関係が高いのは、
となるかと思います。
高い相関関係を持たない区間として、西暦35年~129年の95年間を選び直して、再テストされたということですが、最初の部分 西暦35年~49年は、上記の相関の高い部分になります。
如何でしょうか?
ご指摘ありがとうございます。
確かに私の説明では紀元後25年-49年が高いと言っているので、そのご指摘はもっともです。
実は1年ずつずらして確かめた相関係数の変異は以下のとおりです。
確かに無難に考えるなら、もう少し余裕をもって削るべきなのですが、100年より短い年輪幅での比較はあまり推奨されておらず、こんなギリギリのところを狙ってみました。
比較する年輪幅が短くなると、やはり、偽の照合が発生し、複数の候補が上がってきてしまっています。
ただ、今回は100年分の比較で年代を確定するのが目的でなく、もっとも一致しないであろう年輪部分で比較した時、候補の中に現発表の確定結果と一致するものが含まれるかだけを見たかったため、こんなギリギリな方法でやってみました。
纒向石塚板材と暦年標準パターンEが重なる部分については、200年のうちどの100年をとっても必ず現在確定年が第一候補か有力候補にあがるので、途中に全く無関係の年輪が入っている可能性は少ないと予想します。
いろいろとお手数を掛けます。
以下のように理解しました。
前回の画像2と画像3を比べて見ると、相関関係が高い部分の残った筈の画像2よりも、今回の高い部分を排除した画像3の方が、相関関係がきれいに出ているように見えます。
BC37年から175年の区間に関しては、相関関係が低い箇所がある可能性を調べて見たが、意に反して、高い相関性を持つことが判った。
これが、スレッド主さんの調査した結果と理解しましが、宜しいでしょうか?
コメント者さんの認識で合っております。
ここまでは私の危うい手法ですが、検証プログラム入手前にすでに行っておりました。
そして、相関の高い区間、低い区間があることに気づきました。
相関係数を参考にしながら、可能な限り、相関係数の低い区間を抜き出しました。
100年より極端に短くならないギリギリのラインと考えています。
そのとおりです。
おっしゃる通りです。
これは相関の高い区間、低い区間をさらに細分すれば、その中でも相関の高い年、低い年がランダムにあって、それが、比較とする100年にたまたま含まれるか含まれないかというところにあると思われます。
比較する範囲が100年より長ければ長いほど、こういった影響は小さくなると思われます。こういった揺らぎは100年という短い範囲で比較したことによる弊害と思います。
そのとおりです。
私は暦年標準パターンEに出鱈目な年輪が混ざっている可能性を懸念していました。その箇所として相関係数が低いあたりを予想していました。
ただ、適切なデトレンド処理ができていなかったので専門家の方の動きを当初待ってました。
でも、すぐに公開されたので、早速試しました。
検査プログラムを使用して分かった結果としては、暦年標準パターンEと纒向古墳板材の重なる部分のうち、どの100年を抜き出して照合してもおおよそ同じ結果になるということでした。
もし、暦年標準パターンに怪しい場所があるとしたら別の繋ぎの箇所と予想されるのですが、ただ、独立した暦年標準パターンである木曽ヒノキで纒向古墳板材を照合しても175年伐採となるので、現状、公開データを見る限り、法隆寺心柱100年寝かせた問題のように考古学的には疑問があったとしても、疑うのが難しいというあたりに考えが落ち着いています。
でも、年輪年代法に問題がないかという問いかけは生涯続けていく予定です。それが科学と思います。
意見交換コーナーの皆様へ。
横からすみません。古荘英雄さんの対談会ライブ出席者です。
字面だけのやり取りを読んでいますが、在野でもここまで理解し、話せるんだと、驚嘆しております。なにか先端部分の話で、字面を読んでいるだけでドキドキしております。
こんな深い情報に触れる機会を頂いたことに深謝致します。
「暦年標準パターンE」と「木曽ヒノキの暦年標準パターン」があまり一致しないと、私が考えた件についても、グラフ付きで説明します。こっちの方が理屈はシンプルだと思います。
標準データは標準化されているため、デトレンドする必要がなく、ここまでは検証プログラムを入手する前に気づいていました。
独立した暦年標準パターンでも同じ結果がでることから、暦年標準パターン同士であまり一致しないものの、公開データに誤りがあるとは言えないと認識しました。
ちなみに検証プログラム入手前でも同様の結果が出ていましたが、検証プログラム入手により正しい方法で行うことができました。
暦年標準パターンだからもっと相関するかと予想しましたが、思ったほどではありませんでした。
結論として
こちらもグラフ付きで説明した方が良いとのお話でしたので、自身の向学のためにも、グラフを作っての説明にしました。
解析データを有難うございます。
7/8日のメールの下記の所ですネ。
了解しました。
資料3のグラフを見て、気になったことは:
木曽ヒノキのグラフとパターンEを比べて見ると、パターンEの方が区間によるデータのバラつきが大きいこと。
パターンEを作成する時の元試料樹木のサンプル数が少なくて、「樹齢に伴う長期減衰トレンド」の影響を取り除けていないような気がしました。
パターンEを作成方法を再現してみないと、サンプル数が少ないのかどうかは判りませんが。
パターンE作成の再現。いつかやってみたいです。
本来、とても難しいことですが、基礎データが公開され、デトレンド処理をするプログラムも専門家の方が公開してくれたので、時間をかければ私のような素人でもできる気がしてきました。
有難うございます。
22本のサンプルとパターンEを調べるのは大変ですが、是非、お願いします。
年輪年代学に興味をもっているものです。
歴史については素人です。
奈文研から公開された年輪データを解析した結果をお送りします。
pdfファイルは説明文、zipファイルはPythonソースコードと年輪データです。
よろしくお願いします。
日本古代史ネットワークのスタッフです。
元発言で頂いた PDF ファイルと ZIP ファイルをダウンロードできるように致しました。
「年輪データ解析250807」を読ませて頂きました。調査頂いたこと、その結果と方法をお知らせ頂き、誠に有難うございます。貴重なソフトウエアを開示して頂き、感謝しております。
十分に理解できていない処が有りますが、幾つか質問させて下さい。理解が違っていて、質問がおかしいこともあるかと思いますが、その節はご容赦下さい。
お手数ですが、ご回答頂けると幸いです。
ご連絡ありがとうございます。ご質問に回答いたします。
それらをまとめた改訂版を後日お送りしますので差し替えをお願いします。すべてのデータを計算しましたのでこれ以上行う作業はないと思います。
ご回答を頂き、有難うございます。
了解いたしました。
了解いたしました。
了解いたしました。
了解いたしました。
了解いたしました。
了解いたしました。
了解いたしました。「改訂版」をお待ち申し上げます。
クリアになりました。感謝いたします。
年輪データ解析について改訂版をお送りします。(pdf1件,zip1件)
よろしくお願いします。
日本古代史ネットワークのスタッフです。発言8-5のファイル2件をダウンロードできるように致しました。
残暑お見舞い申し上げます。
この暑さ厳しい時期に大変な作業と解析をして頂き、有難うございます。 感謝しております。
また、幾つかの質問があります。宜しくお願い致します。
「年輪に歴史を読む」では、平均値を算定するとの記述があるので、単純平均化と読めます。
例外的には、「複雑な変動をしめしている樹幹の中心部分、すなわち若年齢期に形成された年輪データ部分を削除して」とあります。
これ以外のことはありそうでしょうか?
この表の中にあるt12/t13/t23 は何を意味しますか?
「表中の1,2,3は上の(1),(2),(3)に対応します。」との記載との関係が、良く判りません。
暦年標準パターンAと外の暦年標準パターンの対比を行って頂き、有難うございます。
作成された表を見ると、「全データパターン」で照合すると良い結果が出ているように見え、驚いています。
個々のデータパターンを単純に平均化した「全データパターン」を標準化したもので、照合するケースと、個々のデータパターンを標準化し、その標準化されたデータを平均化するケースが有るように思います。どちらの方法をとられたのでしょうか?
発表では、「その後、年輪幅による年輪年代測定法の暦年標準パターンが、データの追加によって高精度化しました。」 30年ぶりに柱材を再調査したとの記事が有ります。
光谷氏の手元には、今回公開された暦年標準パターンとは、別の新しい暦年標準パターンが有って、それで計測したと考えるべきと思いますが、若し、コメントを頂けると幸いです。
お手数ですが、お教え頂けると幸いです。
ご質問にお答えします。
1990年公開の[1]には移動平均をとったとか対数をとったとか書いてありますが、その後単純平均でよいと考えが変わったのかもしれません。
最近の文献を見ていないので本当のところはわかりません。
ただし、単純平均より標準化後平均のほうが少し良いのは本文で述べた通りです。
2回行う必要はないのですが、本文で述べた通り実害はありません。
標準化なしは単純平均です。
照合時にはテストデータは標準化が必須です。
暦年標準パターンはすでに標準化されたものか多数のデータの単純平均です。
多数のデータの単純平均は標準化後平均に劣らないというのが今回の発見です。
ただしやはりそのうえで標準化したほうが少し性能は上がります。
AとDは期間が長く重複していますが、データは3本しかありません。
A-3はやはり精度が悪いのか後年の木曽ヒノキパターンから除外されています。
ということでAとDの比較は無理があり、BとCで埋めるべきです。
すべての暦年標準パターンの上位互換なのでどの暦年標準パターンを使っていいかわからないときはこれを使うのをおすすめします。
ikegami-3と期間が合うのは埋木15のみですがまったく照合はとれません。
光谷氏が非公開のデータで照合を行ったのかもしれません。
日本古代史ネットワークのスタッフです。
この後スレッド主さんとコメント者さんのやりとりがあり、「暦年標準パターンF」と「暦年標準パターン補足」との関係について、貴重な指摘がありました。
簡単に言うと、「パターン補足」は「パターンF」の内容を含んでいることになるとのことです。
資料ありがとうございます。
説明を理解するので四苦八苦しているような感じです。
のんびり時間がある時にこのプログラムを動かそうと考えています。
私が気になったところは、説明の文章を読む限り、暦年標準パターンをそのまま使用するのではなく、元データから標準化したりして作り直しているように見える点です。
もし、この理解が正しければ、公開されたデータから厳密な照合って難しいと感じました。
なお、前の専門家の方のやり方は暦年標準パターンは公開されたものをそのまま使い、デトレンド処理が移動平均法より強めだったから高いrとt値が得られたという理解です。
私自身、専門家ではないのでこの理解で合っているのか不安です。
とりあえず、頂きました説明を読んでの私の理解についてのご報告でした。
今回の発言8スレッド主さんの解析は、年輪年代学に沿った本物に見えます。
全て理解し切るのは、難しそうですが、我流ですがやってみました。 真剣勝負ですね。
若干、理解が違ったことは、質問に答えてもらって、判りました。
その通りです。年輪年代法の基本に沿った方法です。
しかし、不思議なことは、この方式でt値を出すと、一ヵ所だけで数値がきれいに伸びます。
光谷さんの書籍に書いて有ること、講演で話したこと、ヨーロッパの年輪年代の情報のいずれも、3.5以上の高い数値を出した複数の候補ポイントで、グラフ(対数グラフ)を描き、 そのグラフを、人が見て判断して年代を決定している。
特にヨーロッパでは、国をまたぐ複数の学者が見て、全ての人が、合意することで、その候補ポイントが決定になるそうです。
処が、今回のこの解析では、そんな必要もなく、一ヵ所(特定年)に定まります。
余程、この暦年標準パターンなるものが、良く調整されているのか、とも、考えたくなります。
不思議です!
尚、
このように、光谷氏は、書いて、話していますが、具体的にそのやり方と外のやり方を比較するなどしてくれたのは、発言8スレッド主さんが初めてで、興奮しながらその結果を読んでいました。
前の専門家(発言6)の方は、別の方法をとっていたように思います。 (詳しく調べることができていませんが。) この方の場合も、高いt値が出ていたので、驚いていました。
二人の専門家が行った結果、共に、きれいに一ヵ所でt値が出ていることは、不思議です。 ヨーロッパの専門家たちの苦労が、何故、水谷氏の暦年標準パターンでは、出ないのか。
プログラムが公開されているので、動かして、テスト稼働してみて頂けると有難い!
今後共、宜しくお願い致します。
いろいろお教えいただきありがとうございました。
今回の検証を見ても、前の方の検証を見ても正しく検証できているので、年輪年代法によって出された結果は正しいだろうと私も予想します。
また、以前、相関係数が低いことについて私は懸念していたのですが、200年とか長い期間になると、r値が少し低くてもt値は高くなので、見た目は似ていないように見えたとしても信頼できると、今は懸念がなくなりました。
なお、前回のメールで私が気になったのは、実は以下の点です。
公開された暦年標準パターンEを使用し、移動平均法でデトレンドした纒向石塚板材の年輪と マッチングさせるだけで追検証ができると私は考えていました。
そのあたりを変える必要があるのなら、光谷氏は果たしてどのような方法でマッチングさせたのだろうかと、気になったのはそのあたりです。
年輪年代法の結果が正しいことは分かったのだけど、光谷氏の手法が分からない。
今、もやっとしているのはその部分です。
ただ、私にとって気になっていたのは年輪年代法の結果なので、30年来の謎が分かり、今、気分すっきりです。
とのことですが、私の方は、混迷の最中です。
ここまで、きれいに判ったので、確認の作業をしてみましたが、光谷氏の書いた「年輪に歴史を読む」に記載されたパターンAのグラフが、開示されたデータで作成されたグラフとは、大きく違いが有ることが判明。
その外、発表された記事の中にあるグラフが、やはり、開示データとは隔離しています。
文章・記事に発表された根拠が、開示データとは異なる。
私の方で、何かやり方を間違えて、違えてしまったのかも含めて、調査、検証が必要です。
開示データの作られた時期も、確認の必要性が出てきました。
科学的な検証として、確かに私もそのあたり気になります。
私の方もすこし気がかりに思うところはあります。
それは結果というより光谷氏の手法が読み取れない点です。
公開された暦年標準パターンEを使い、移動平均法で纒向石塚板材をデトレンドすれば 高いt値が得られると考えていました。
でも、暦年標準パターンEを作り直したり、強めのデトレンドが必要となると、当時、光谷氏は「みきり発進で結論を出したのではないか」など。
いろいろ邪推してしまいます。
当時の発表のグラフをあまり見ず、年輪年代法の結果のみ気にしていたので、私は専門家の二人の見解で十分満足してしまいましたが、科学的な検証としてコメント者さんの懸念、まったくその通りに思います。
なるほどです。
私の方の最後の疑問は、以下の条件で高いt値が得られるかです。
他の方の意見が出てくるのを、さらに待ちたいところです。
メールを頂き、有難うございます。
以下の部分が気になります。
この中で、『暦年標準パターンEを作り直したり』は、「暦年標準パターンEに対して、移動平均法の操作を加え」r値及びt値を計算した。という意味でお使いになっていると思います。
強めのデトレンド(変化傾向を除去する:樹木が若い時に早く幹を太らせる傾向など削除する)ですが、光谷さんの書いた手法としては、「移動平均法」だけです。
光谷さんの記述から見ると、人に依頼して、プログラムを作成してもらい、以下の操作を行ったように記述されています。
暦年標準パターンから移動平均法を加えたパターンを作成。一方でサンプルの年輪巾パターンにも同様の操作を加え、双方を対比照合して、r値とt値を計算する。
従って、「サンプルの年輪パターンと暦年標準パターン」が揃えば、プログラムを稼働して、自動的に、t値を得ていたと推定します。
光谷さんが書物で/講演会で、強調していたのは、
計算部分を省いて、見切り発車したことは、想像し難い所です。
次に、
この件ですが、OX様の「奈良文化財研究所公開の年輪データの解析 2025年8月13日」の47頁以降の記述で、上記の通り行った結果が記されています。
175年にt値の高いピークが発生しています。
ご確認下さい。
開示データ自体は、良く整合性のと取れたデータになっているように見えます。良すぎる処が、気になりますが。
ありがとうございます。いろいろ分かった気がします。
当時、t値でも判定できなったのですね。私としては貴重な情報です。
公開データからだけでは
というところまでは予想できませんでした。
この対数グラフというのが移動平均法と似た効果が得られるならようやく納得です。
また、「暦年標準パターンから移動平均法を加えたパターンを作成」というのも私の中ではあり得ない発想でした。
実は標準パターンを標準化すれば、相関係数が高くなり、t値も高くなるのは分かっていましたが、これはやってはいけない手法だとやるのをやめていました。
(もっとも公開された標準パターンが標準化されたものでないならやる必要があると思いますが)
もし、「標準パターンを標準化する」という方法が正しければ、マッチングに使用しなかった「標準パターン」ではなく、マッチングに使用した「標準パターンを標準化した標準パターン」についても奈文研は公開すべきだったのかなと思いました。
こちらではt値が7.2ありますが、
これは私が言う「1. 暦年標準パターンEは公開されたものを使用する」ではなく、暦年標準パターンを移動平均法でデトレンドしたものを使用した結果と考えています。
結果的に年輪年代法の結果が正しいとなるので大した話ではないのかも知れませんが、「公開されたものを使用する」か「公開されたものに手を加える必要がある」かは私の中では結構重要なことでした。
それゆえに、前回のメールで、こういう点が気になったと私は述べた次第です。
失礼しました。
この意味は、暦年標準パターン側では移動平均法を使わず、サンプルの纒向石塚板材では、移動平均法を使い、という、片寄った方法で対比・照合してみる。との意味だったのですね。
余計なことを書いて、失礼いたしました。
こちらこそ説明が足りておりませんでした。
実は以前、丸地様から移動平均法を使っているという話を聞き、公開された暦年標準パターンEをそのまま使用し、纒向石塚板材を移動平均法でデトレンドして検証したのですが、高いt値が得られず失敗しました。
実は木曽ヒノキの標準パターンではもう少しましな信頼度は得られたのですが、木曽ヒノキの標準パターンは当時存在しなかったので、当時、光谷氏はどうやってマッチングできたのだろうと少し疑問に思っていました。
でも、光谷氏が暦年標準パターンをデトレンドしていたとしたら、
言い換えれば、
暦年標準パターンEのデトレンドが不十分だったと考えれば、かなりすっきりした気がします。
綿密な検証結果をありがとうございました。
素人の基本的な質問で申し訳ないのですが、5年移動平均法による基準化は年輪試料の両端の年輪幅とそのすぐ内側の年輪幅の基準化はできないはずですが、どのように処理しているのでしょう。もし、両端とその内側を除いた基準化値でコンピュータ処理しているのであれば、たとえば、コンピュータによる照合年代が592年と出た場合、実際の最外側年輪は2を加えて594年であると理解することになりますが、この理解でよろしいでしょうか。
同様に、たとえば、-220年と出ていれば、実際の最外側年輪は-218年のものと考えてよろしいでしょうか。
先ほどの質問の追加ですが、光谷さんたちは、5年移動平均法による基準化をしたうえで(この基準化値は100を掛ける前の値ですので、1を基準値としてその前後に散らばる値)、その自然対数を取ってコンピュータ処理をしているようですが(ですから0を基準値としてその前後に散らばる値による処理)、自然対数を取る前の基準化値での解析も、自然対数を取ってからする解析も、結果は本質的に同じであると考えてよろしいのですね。素人の質問でごめんなさい。
素人の質問の続きでもうしわけありません。
今回公表された7つの暦年標準パターンについては、確かにこの位置で接合するのが最適であることも、すでに確認済みであると考えてよろしいのですね。
つまり、互いを1年ずつずらして、r値、t値が、確かに指定通りの位置で最高になっており、ほかの場所で同程度の高さになる位置はないということが確認済みであると考えてよろしいのですね。暦年標準パターンの接合に不備があるのではないかという疑い説がありましたので、確認までさせていただきました。