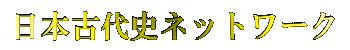古代史を解明する会(解明委員会)
「解明委員会」の名称を変更します。
オープンで誰でも参加できる会なのに!「委員会は変」、という声があり、2022年7月より「古代史を解明する会」と変更いたします。しばらく、両方の名前が混在しますが、ご容赦下さい。
参加方法
オンラインで開催しています。多くの会員の参加をお待ちします。
- 会員の参加希望者はメールで kaimei@nihonkodaishi.net へ、氏名を記してお申し込み下さい。
- 非会員の参加希望者はメールで kaimei@nihonkodaishi.net へ、氏名・フリガナ・〒・住所・電話を記して、一般会員の入会希望と書き添え、参加申し込み下さい。
参加申し込みをされた方に、参加招待・案内をメールでお送りします。
初めての方でも、PC、タブレット、スマホが有れば、簡単にできます。初めての方には、初歩的な使用方法をお知らせし、予行演習も行います。その旨記してお申込み下さい。思った時にやってみましょう。お手伝いします。
解明されてきた古代史テーマ
2020年12月以来のほぼ毎月の活動の結果、解明されてきたテーマが出てきましたのでお知らせします。古代史の新しい考え方・説として、皆さまに、ご検討頂けると幸いです。
- 1. 神話の時代を考古資料と照合
-
記紀神話を歴史として解釈し直して、考古資料と突き合わせると歴史的事実として見ることが可能。
- 天照大神は、須玖岡本の王墓に埋葬。西暦57年後漢の光武帝より金印受領。
- 三雲南小路王墓は、邇邇芸命の墓。西暦107年後漢に朝献した倭国王師升。
- 出雲国譲りの建御名方神の記述は、青谷上寺地遺跡、吹上遺跡・高地性集落斐太遺跡・諏訪大社に適合。国譲りに派遣された建御雷之男神などの移動事実は、鹿島・香取神宮に残る。
- 神武東征は、途中経由地の筑紫国の岡田宮・阿岐国の多祁理宮・吉備国の高島宮の所在地が確認でき、大阪湾から大和へ侵攻のコースなども遺跡・地名で確認できた。神武軍の熊野灘での遭難以降のコースは、地名・神社伝承で継承される。
古事記・日本書紀の神話は、戦後、歴史学者に否定され、抹殺されてきたが、神話のストーリーが遺跡と対比することで、多くは、事実として確認できた。これは、当会の大きな成果と云える。
43. 「文献と考古の対応:神話の時代全体」(2024/08/10)などをご覧ください。
- 2. 古代朝鮮と日本の歴史の関係
-
- 日本の歴史では、古代の人・物・文化は、全て朝鮮半島を経由して渡来したとの教育が行われてきた。
- しかし、韓国の中等教科書・歴史博物館の展示記述では、縄文人が朝鮮半島に住み、遺跡を遺していることが明記され、朝鮮歴史書「三国史記」には倭人が新羅王となったことが記されている。
- 古代史教育では、韓国と日本のギャップが大きい。調べて見ると、下記のことが判った。
- 一部の例外はあるが、縄文時代から弥生時代では、日本の縄文人が韓国へ進出し、弥生人=倭人も、日本から土器・水田稲作・弥生文化をもって朝鮮半島南部へ進出していた。(朝鮮半島から日本へは無かった。)その後、白村江の戦い(663年)で状況は一転して、朝鮮半島から日本へ移動が行われたた。
- 例外としては、韓国の松菊里遺跡などから水田稲作・支石墓が、西北九州縄文人の手で、日本へ持ち込まれた。この文化は長続きせず、弥生渡来人との戦いの後で、消滅した。
32. 「古代朝鮮と日本の歴史」(2023年8月12日)をご覧ください。
その外のテーマも解明が進行中です。
カテゴリーに分類したテーマの一覧表は ➡ 分類別テーマ をご覧ください。
予定
- 「邪馬台国・卑弥呼と天孫族の関係」 2025/07/19(土)
- タイトル未定 2025/08/16(土)
7月19日は、卑弥呼と天孫族との関係を明らかにします。一方で、邪馬台国の比定地が明確になり、神話の時代が出来事が実際に考古資料で確認でき、天孫族と出雲族との抗争が実存したことから、中国資料に記された卑弥呼との関係を検討します。
活動記録
※ カテゴリーに分類した一覧表は
➡ 分類別テーマ
- 「古代史を解明する会」の指針
-
- 古代史研究の方法論(2020/12/05)東京 実施済
- 以下の記録は バックナンバー1 に記載
-
- 日本人の起源(2021/01/23)東京 実施済
- 弥生時代から古墳時代(2021/02/27)東京 実施済
- 邪馬台国論(2021/03/27)東京 実施済
- 科学的年代測定法とその適用(2021/04/24)東京 実施済
- 日本書紀・古事記・風土記の世界(2021/05/22)東京 実施済
- 大陸との交流「徐福論」(2021/06/26)東京 実施済
- 以下の記録は バックナンバー2 に記載
-
- 日本人の起源(沖縄の古代歴史の真実は?) (2021/07/31)東京 実施済
- 弥生時代から古墳時代(神武東征) (2021/08/28)東京 実施済
- 邪馬台国論(唐津上陸説に根拠はあるか?) (2021/09/25)東京 実施済
- 科学的年代測定法とその適用(年代測定法の相互関係と課題)(2021/10/09)東京 実施済
- 弥生時代から古墳時代(出雲勢力??)(2021/11/13)東京 実施済
- 大陸との交流(タミル語と日本語)(2022/01/15)東京 実施済
- 以下の記録は バックナンバー3 に記載
-
- 日本人の起源「沖縄と宝貝」(2022/02/12)東京 実施済
- 弥生時代から古墳時代 「水田稲作と弥生人渡来」(2022/03/12)東京 実施済
- 邪馬台国論「卑弥呼の使者を迎えた中国・魏の外交情勢」(2022/04/16)東京 実施済
- 「年輪年代法の情報公開請求とそれに関する訴訟について」(2022/05/14)東京 実施済
- 解明委員会で取り上げるべきテーマ(2022/06/11)東京 実施済
- 大陸との交流(長江文明)(2022/07/09)東京 実施済
- 以下の記録は バックナンバー4 に記載
-
- DNA・日本人の起源(2022/08/27)東京 実施済
- 日本における農耕と稲作の起源(2022/09/10)東京 実施済
- 「大和政権成立とその直後に起きたこと」~記紀と考古学から(2022/10/08)東京 実施済
- 「天孫降臨と神武東征」仮説(2022/11/12)東京 実施済
- 「弱体の神武は何故勝利を得ることができたのか?」
(2022/12/10)東京 実施済 - 「箸墓古墳は誰をまつる古墳か?」(2023/01/21)東京 実施済
- 以下の記録は バックナンバー5 に記載
-
- 「先史時代の日本語と中国語の関係」(2023/02/11)東京 実施済
- 「欠史八代 大王非存在と神武=崇神説の検証」(2023/03/11)東京 実施済
- 「神武東征は有ったのか? 長浜浩明氏の動画論評」(2023/04/08)東京 実施済
- 「朝鮮半島の古代歴史を学ぶ」(2023/05/13)東京 実施済
- 「寺沢薫著『卑弥呼とヤマト王権』について」(2023/06/10)東京 実施済
- 「寺沢薫氏の邪馬台国論を論じる」(2023/07/08)東京 実施済
- 以下の記録は バックナンバー6 に記載
-
- 「古代朝鮮と日本の歴史」(2023/08/12)東京 実施済
- 「西遼河起源説+𝛼」(2023/09/09)東京 実施済
- 「天孫降臨と史実の関係」(2023/10/07)東京 実施済
- 「邪馬台国と高天原の関係」(2023/011/11)東京 実施済
- 「日向三代の記述の理由」(2023/12/09)東京 実施済
- 「文献と考古資料の対応:天孫降臨・日向三代」(2024/01/13)東京 実施済
- 以下の記録は バックナンバー7 に記載
-
- 「文献と考古資料の対応:天孫降臨・日向三代」をふまえての意見と議論(2024/02/10)東京 実施済
- 「日本神話」について (2024/04/06)東京 実施済
- 「文献と考古資料の対応:出雲国譲り」(2024/05/04)東京 実施済
- 「文献と考古資料の対応:神武東征」(2024/06/08)東京 実施済
- 「記紀編纂の目的他」 (2024/07/06)東京 実施済
- 「文献と考古の対応:神話の時代全体」(2024/08/10)東京 実施済
- 以下の記録は バックナンバー8 に記載
-
- 「日本語・琉球祖語から見た日本人の起源」(2024/09/14)東京 実施済
- 「土井ヶ浜遺跡の人骨DNA解析結果」(2024/11/09)東京 実施済
- 「新聞記事を見ながら日本人の起源を検討」(2024/12/07)東京 実施済
- 日本人の起源~最新のDNA成果を反映する(2025/01/18)東京 実施済
(2025/02/09 New!) - 一部勝訴! 年輪年代法の情報公開請求裁判の報告と今後の方針(2025/02/22)東京 実施済
(2025/03/03 New!) - 邪馬台国論争を振り返る~邪馬台国論争と日本国家の起源(2025/03/15)東京 実施済
(2025/04/12 New!)
- 以下の記録は バックナンバー9 に記載
-
- 「邪馬台国論争の解明」(2025/05/03)東京 実施済
(2025/05/07 New!) - 日本書紀の紀年を復元する「無事績年削除法」(2025/06/14)東京 実施済
(2025/06/20 New!)
- 「邪馬台国論争の解明」(2025/05/03)東京 実施済
1.「古代史研究の方法論」(2020年12月5日)
- 第1回 解明委員会「古代史研究の方法論」(2020年12月5日)は、無事に開催し、終了いたしました。
- 池袋のとしま区民センター 会議室502に集合された4名とオンラインで参加された7名で開催されました。時間は、13:15より15:00。
議事は、
- 事前に、事務局の丸地から、参加者全員に、古代史研究の方法論(たたき台)と「資料批判の精神」と称する文章を配布。
- 議事が開始され、丸地より、方法論(たたき台)を画面に表示しながら、説明を行った。
- 古代史の問題点 → 知りたい内容
- 重点テーマ → 目的範囲と基本的手法
- 目的とする歴史のレベル
- 歴史解明の基盤
- 歴史解明に必要とする周辺学問分野
- 周辺分野を用いた歴史解明の実例の提示
- 集団で行う解明作業の手順の提示
- 解明作業の原則 ① 証拠を示し、論理的に行う 史料批判を行うこと
- 解明作業の原則 ② 時間・空間を重視 表・グラフ・地図・模式図の採用
以上の説明を行い、出席者から自己紹介と意見を求めた。
なお、丸地より説明が行われた古代史解明の方法論(たたき台)に関しては、当日の録画では有りませんが、再演し、YouTube の動画としてご覧頂けます。
- ★ 資料(たたき台) → 古代史研究の方法論―基本レポート.pdf(約5.6MB)
- ★ 動画 YouTube 動画リンク → https://youtu.be/9dWRh9ZzJdY
幾つか、具体的な提案・意見が上がったので記す。
- 縄文時代から弥生時代への変革の時期について。弥生以降の時代に大きな影響を与えたことなので、取り上げを要請する。
- 事務局より、日本人の起源の中で、弥生渡来人を大きなテーマと見ており、取り上げる予定している。大きな影響を与えたこと認識しており、重要なテーマと理解している。
- 日本人の起源の中で取り上げて下さいと了承。
- 古事記・日本書紀の取り扱いについて、二人の方から同様の発言があった。時の官僚が行った作文=公文書が、記紀のベースになっているはず。現在の公文書も、ウソが含まれており、古代でも同様であったと推測される。文献史料をして取り上げる場合には、十分に留意すべきだ
- 古事記・日本書紀に関しては、どなたかが、その成り立ちや、留意点をまとめて、レポートし、それを理解した上で、論議に入った方が良い。
- 根拠となる事実を示すとのことだが、それが根拠となっているのか、根拠のある論旨なのかの判定は、誰が行うのか? との質問が出た。
- 事務局丸地の方からは、誰か特定の人が判定することは考えない。複数の答えが残る可能性があり、どうしても一つの答えに集約させるようなことは行わないと回答。
- 文字ばかりの羅列では無く「図表・グラフ・地図化」することで、認識の共有を図ることが提起されたがこの中で、地図化に関しては、Googleの地図アプリを使う方法が有り、使いやすいことが示された。
この提案に関しては、後日、地図アプリ(Google Map (API)/Google Earth)を利用する方法について、取りまとめ、ガイドとなる資料がアップされたので、それをご覧ください。
→ 「Google サービスで歴史研究」のページ(野口理事のWebサイト)
- ☆ 多くの方々の発言から、丸地の説明した方法「たたき台」を認める発言があり、基本的な賛同を得た。
- 一つの方法論と原則がしめされたもので、会を重ねる中で修正して行くことで了承された。
- ◆ 次回の「日本人の起源」について
-
- 本日の「古代史研究の方法論(たたき台)」に沿って、運営することとする。
- 日本人の起源に関して、概要と課題・関連学問などをレポートする人を求めたが、手を挙げる人が居なかったため、丸地がレポートすることとした。
- 次回開催は、新型コロナウイルス感染拡大の恐れがあるため、全面的にオンラインでの会議とすることが提案され、了承された。
時間的には余裕がありましたが、以上をもって終了としました。